赤ちゃんの時には、ミルクを飲んだらスヤスヤ~
やさしい言葉がけでスヤスヤ~
幼稚園に行くようになり、昼間の活動が多くなったから
夜はぐっすり寝てくれるだろうと思った。
でも、
何時になってもグズグズ~
ベットに入ってもグズグズ~
どうして寝てくれないのかしら?という悩みが、パパやママから多く聞かれます。
特別に、体調が悪いわけでもない。
食事もそれなりに食べている我が子が、夜にぐっすり寝てくれないと気になりますよね。
あの大リーガーの大谷翔平さんの睡眠時間なんて、すごい時間らしい。
時間があれば、寝ていた!そして、寝る子は育つで、大きくなった!!
睡眠が、成長に大きな影響をもたらすのならば、ぐっすり眠る子どもになってほしいですね。
いっばい寝て、大谷翔平さんのようにたくましく育ってほしいと願いますよね。
私は38年間保育者として、また現在、保育者養成大学の非常勤講師として
子どもの様々な問題の相談にのってきました。
子どもがたっぷり眠って、心も体も健やかに育つような【眠り】のサポートの仕方について
お伝えいたします。
眠りを誘うサポート
赤ちゃんでもぐっすり眠れるようにするには、【ねんトレ】という訓練や練習が必要なのです。
子どもがよく眠るためには、ちょっとした魔法のようなサポートによって習慣づけることで
ぐっすり眠れることが増えてきますよ。
寝るということのルーティンを決める
眠る準備は、ちょっとした魔法みたいなもの。
ご飯を食べる。歯磨きをする。幼稚園や保育所に行く。先生たちにご挨拶をする。お友達と遊ぶ。
給食を食べる。お昼寝をする。おやつを食べる。絵本を読む。・・・
あげればキリはないけれど、毎日の子どもの生活リズムは決まっています。
考えることなく、子どもたちはこの活動を毎日こなしています。
寝ることだって毎日の生活の決められた活動の一つなんです。
だから眠ることができるようにルーティンを決めてあげれば、自然と「寝る」習慣がつくはずです。
家庭によって時間帯は様々ですが、まずはお子さんの日中の活動量や体力などを考えながら、
夕ご飯から寝るまで、何をするのか決めましょう。
夕ご飯を食べる ⇒ お風呂に入る ⇒ 歯を磨く ⇒ お布団を敷く(ベッドに入る)
⇒ 軽くストレッチや深呼吸 ⇒ カモミール大好きなぬいぐるみをそばに持ってくる ⇒
絵本を読んでもらう ⇒ 電気を消す
というように・・・毎日、同じ順番で・・・
このルーティンを習慣づくまでやってみるのです。
体が寝るのだということを覚えてきたならば、お子さんはスヤスヤ~
寝るための環境づくり
ホワイトノイズを重視
寝るために効果的な音や音楽のことをホワイトノイズと言います。
かつて深夜になると、TVは放映終了となり、画面から映像が消えました。
そして次に現れたのが、砂あらしのような画と音。
この砂あらしの音を聞かせると、ぐずっていた赤ちゃでもすぐに寝てしまうと言われていました。
この砂あらしの音は、赤ちゃんがお母さんの胎内にいた時を思い出させ、安心するからだそうです。
今、この砂あらしの映像を目にすることはなくなりました。
でも身近なところにも、この砂あらしのような音はあるんです。
子どもだって、大人だって、このホワイトノイズは眠りを誘う魔法の音です
眠りに効果的なファンノイズ
波の音
風の音
雨だれの音
川のせせらぎの音
ママの心音
換気扇の音
チクタクチクタク時計の針の音 など
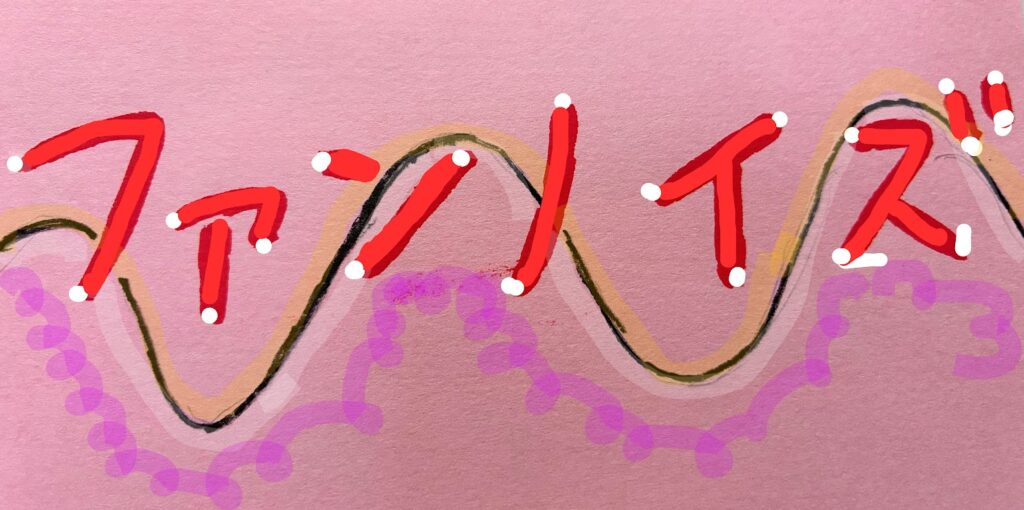
大人でも疲れていて、これらの音を聞いていたら、なんだか眠くなってしいますね。
これらの音は、眠りを誘います。
音の波長としたら、大きな波のうねりがゆったりゆったり押し寄せてくる感じですね。
電子ノイズも効果あり
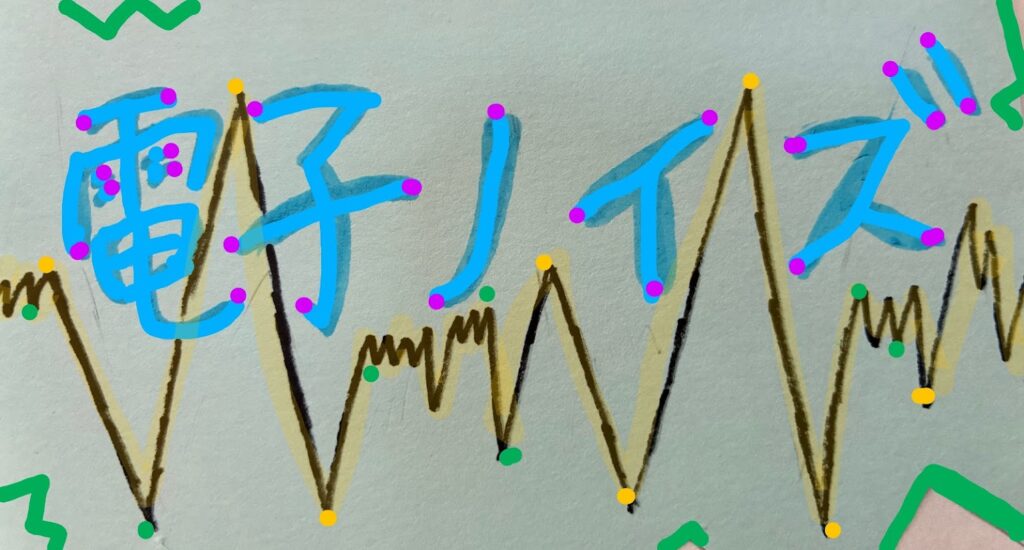
パパが、子どもの側でパソコンをカチャカチャ
ママが、髪を乾かすためにドライアーをかけている音
お兄ちゃんがゲームを楽しんでいる音
台所の換気扇の音 など
電子の音であっても、リズムが一定のものならば眠りを誘うのです。
ただし、子どもによって個人差はあります。
眠りにNGな音
大人でも、これはイライラするという音がありますね。
せっかく落ち着いているのに、突然の大きな物音にびっくりして、目が覚めた!という体験。
子どもが寝ている間は、避けたいですね。
とくに、寝入りばなには気を付けましょう!
テレビやラジオの突然の大きな音
隣接した道から工事の音
窓から聞こえる大勢の大声の話し声
かみなりの音
車のエンジン音 など代表的ですね。
- 突然の大きな音(工事の音 食器を落とす音 ドアのバタン音 大声 叫び声)
- 高い音や鋭い音(インターホン アラーム 目覚まし音)
- ボリュームが大きい音(バラエティ番組やアクション映画 それに反応する人の声)
- 複雑な重なっている音(複数の人の話し声 カフェのような環境音)
寝室の環境
- 明るさ
スクリーンは早めにオフにします
特にブルーライトは、眠りを妨げますね。
寝る1時間前には、スマホやテレビも消しておくといいですね。
暗さは、眠気を誘うメラトニンの分泌を促します。 - 温度と室温
暑すぎず寒すぎず。
季節に合った快適な環境を整えると自然に眠気が訪れます。
ただし、大人と子どもの体温は違い、体感温度にも個人差がありますね。
部屋に、温度と湿度計を置いておくと、お子さんが眠るのにいい室内環境がはっきりしますよ。
それを見て調整しましょう!
寝る前のリラックスタイム
大人でも心配事や不安があれば、なかなか寝つけません。
そんな気持ちを軽くしてあげるためにも、リラックスできるようにサポートしてあげましょう。
- 1日を振り返って、楽しかった?
パパやママも毎日の生活が大変であっても、お子さんの前では、そのイライラは押さえてくださいね。叱られたり、時には泣いたりしているといい睡眠にはなりません。
「今日、どんなことが楽しかった?」といい事を思い出させてあげましょう。 - 寝かしつけミュージック
お子さんの大好きな音楽をかけてあげるといいですね。
好きだからと言って、ハイテンションになる音楽は逆効果になるから、ご注意! - アロマ
寝室がなんとなくいい匂い~
ステキな夢を見ることができそうですね。
ラベンダーやカモミール、スィートオレンジ、ヒノキ、サンダルウッド、ゼラニウムなどたくさんありますね。
好きな香りを選びましょう。
安心して眠るためのお気に入りグッズ
〈お気に入りのぬいぐるみ〉
そばに置いておくと安心できる相棒です。
大人から見て、「え~?こんなものが?」というものもあるでしょう。
赤ちゃんの時からの、ずっと大切にしていた愛用品はありますか?
〈毛布やタオルケット〉
スヌーピーに出てくる男の子がいつもタオルケットを引きずっていますよね。
あの温もりが、気持ちを落ち着かせてくれるのです。
いずれも、毎晩握っていたり、時には口にくわえたりするのですから、衛生面には気をつけましょう。
しかし、夜までに乾かなくてお子さんが困ったことにならないように、ご注意!
食事
食事や運動は、子どもの睡眠の質やリズムに大きく影響します。
ただ眠らせるのではなく、睡眠の質を考えましょう。
・寝る直前の食事はNG
満腹ならば眠くなりそうなものだけど、胃が動いていると体が休まらないのです。
眠ったとしても、浅い眠りです
せめて、夕食は寝る2・3時間前までに済ませましょう。
・糖分のとりすぎに注意
ジュースやお菓子などの糖分は、テンションが上がってしまい、寝つきが悪くなりますよ。
・安眠を助ける栄養素は?
例えば、バナナはマグネシウムやトリプトファンが含まれているから、リラックス効果があります。
どうしてもお腹が空いて眠れない時には、このバナナを軽いおやつとして寝る前に少しならば大丈夫
です。
運動
本物の時計を見なくても、体は一日の時間を覚えています。
食事の時間が近づいてくると、お腹が空いてきますよね。
外が暗くなってくると、なんとなく眠くなってくる。
これは、体内時計が一日の生活時間を覚えているからです。
外国に行ったり帰ってきたりした時に、時差で体がきついというのも、体内時計が本当の時間についていっていないからです。
運動をすることで、この体内時計を整える効果があるのです。
・日中の適度な運動は、睡眠を深くします。
公園で遊んだり体を動かしたりすると、心地よい疲れからか、夜になって自然に眠気が訪れます。
でも激しい運動をしたり疲れすぎたりすると興奮してしまい、なかなか寝付けないことも、、
お子さんの体力に合わせて、楽しく運動させましょう。
・運動は寝る数時間前までです。
運動直後は、興奮状態になりますから、寝る直前の激しい動きはやめた方がいいです。
仕事が遅くなったパパが帰ってきた時、もうすぐ寝ようとしていた子どもたちと大はしゃぎで遊ぶ
ことがありますね。
結局、子どもたちはすっかり目が覚めてしまった~困った、困ったということに・・・
絵本
眠れない夜には、絵本の魔法です。
ゆったりとしたリズム、やさしい絵、ママのやわらかい言葉、静かな物語が心を落ち着かせてくれますよ。
- 『ねむたいねむたいねずみ』ささきまき・作
どんどん眠くなっていくねずみくんのお話 - 『おつきさまこんばんは』林明子・作
おつきさまが夜空に顔を出して、優しく微笑む絵です。
短く出静かな文章が心を穏やかに~ - 『いいこって どんなこ?』ジーン・モデジット・作
”いい子”の定義を考えながら、自分の存在が愛されていることを実感できる安心感のある絵本 - 『ねないこ だれだ』せなけいこ・作
少し怖がらせて・・・寝る気にさせるユニークな絵本。子どもなりに共感できて、効果てきめん! - 『おやすみ、ぼく』アンドリュー・ダッド/エマ・クエイ・作
眠る準備をする僕の姿がやさしく描かれている絵本。「眠るっていいな」と思わせてくれます。
まだまだたくさんありますよ。
寝ることが描かれていない絵本でもいいのです。
お子さんは、どんな絵が好きかな?どんなお話を聞かせたら落ち着く?
お子さんの大好きな絵本を、ママの声で読んであげたらいいのです。
心が落ち着くことで、きっと眠りの世界に入っていけるはずですよ。

毎日、違った絵本を読んであげる必要はありません。
・・・M子ママの失敗・・・
「さあ、今晩はこのお話をしてあげよう」と張り切ってお話を覚えたM子ママ
M子ちゃんがお布団に入って、ママはそばで覚えたてのお話を張り切って語り始めました。ママは、語りが詰まらないようにと一生懸命でした。
それなりに、M子ちゃんの眠りを誘うお話だったのです。
ところがM子ちゃんは急に
「ママ!そのお話はもういいから・・・いつもの桃がどんぶりこのお話してよ」
お話のレパートリーが少ないM子ママは、いつもは定番の『ももたろう』のお話をしていたのです。
M子ちゃんにとっては、ママの「どんぶらこ~どんぶらこ~」の声が一番落ち着くし眠りに誘うお話だったと気づいたのです。
お母さんにおススメ絵本
上記のM子ちゃんのママの気づきのように、いろいろな絵本を読むことも、眠りに関係した絵本である必要はないのです。
ママやパパ、時にはおばあちゃんが安定した気持ちで寄り添ってくれることが大切なんです。
そして、なぜお子さんが眠れないかを理解してあげることです。
お子さんの気持ちをあたたかく包んであげること。
時には、今、していた家事や趣味の手を止めて、お子さんの眠りと向き合うという事なんです。
そういうことに気づかせてくれる一冊です。
お子さんに読んであげる前に、ママやパパ!読んでみませんか?
『ねむれないの?ちいくまくん』(評論社)
マーティン・ワッデル 文 バーバラ・ファースト 絵 角野栄子 訳
おやすみの時間なのに、ちいくまさんは、眠れません。
一生懸命に眠ろうとするのに、暗いのが怖くて眠れません。
おおくまさが、一番大きなランプをつけてくれたのに
それでも眠れません。
(おおくまさんは、自分の読書がちいくまさんによって邪魔されるから、ちょっと不満にも
感じていました。)
でも、おおくまさんは怖くないよって、ちいくまさんにあることを教えてあげました。
とってもいい方法でね。
このお話を読んで、2人のママの子育て経験談を思い出しました!
赤ちゃんが眠らなかった経験があるママ2人の会話
A「うちの子は、なかなか眠らなかったわ。」
「原因はわからない。どんなに部屋を静かにしてやっても・・・」
「だから、夜中であっても外に抱っこして、連れ出していたの。」
B「そうそう、うちの子もなかなか眠らなくて苦労したわ。」
「私も気分を変えようと、外に出て、我が子と一緒にお星さまを数えてた!」
「夜中の3時!」
「そうしたら、向こうから新聞配達が来るのが見えて、まさかこんな姿が見られたらと
慌てて物陰に隠れたり・・・(笑)」
A「ほんとね。まさかまさか~そんな夜中に赤ちゃんを抱っこした女の人に出会うなんて、、
新聞配達の人だってビックリされるよね~」
B「でも、我が子が大きくなった今、あの頃が懐かしいのよね。」
「我が子とあんなに密な時間を過ごせるなんて!我が子は私にしっかり抱っこされて」
A・B 「ママとしての至福の時!」
A「それに、あんなに夜空の星を眺めることなんて、なかなかないよね~」
B「我が子が寝らなかったからこそ、私は流星群だって見ることができたわ。」
A「私たち、我が子が寝なかったからこそ、他の人にはできない経験もしたということね。」
いつかは、今、赤ちゃんが眠らないという辛さから抜け出します。
AママとBママの2人にとっては、子育ての中の懐かしい思い出に変わっていました。
まとめ
この記事は、3歳~6歳のお子さんが眠れないという悩みにお答えしました。
赤ちゃんの時から【ねんトレ】・ねんねんトレーニングができていると、幼児になっても体は眠るということが身に付いていますから、ママやパパの悩みはそれほど大きくならないで済みます。
ぜひ、【ねんトレ】についても読んでみてください。
子どもとって〈寝ること〉は、成長(体と脳と心)にとって、とっても大切なことです。
それもただ眠るのではなく、いい睡眠でなくてはなりません。
1歳児が保育所に入園してきた時、入園1ヶ月は特に睡眠に気をつけるべきだと
私たち保育者は保護者にお願いしてきました。
新しい環境に対して体がストレスを感じ、睡眠時に血圧・脈拍の異常が出てくる恐れがあり
そのことが睡眠時の突然死を引き起こすことがあるのです。
朝起きた時、元気な子どもの顔を見たいですよね。
一番大切なことは、毎日、子どもの活動に無理をさせず、ストレスを与えず
睡眠時の環境もいつもと同じにということを大切にしてあげてくださいね。
たっぷりの眠りは、食欲を増し、豊かな生活につながります。
あの大谷翔平選手のようなたくましさも夢ではありませんよ。
今夜もいい眠りを~
おやすみなさい!
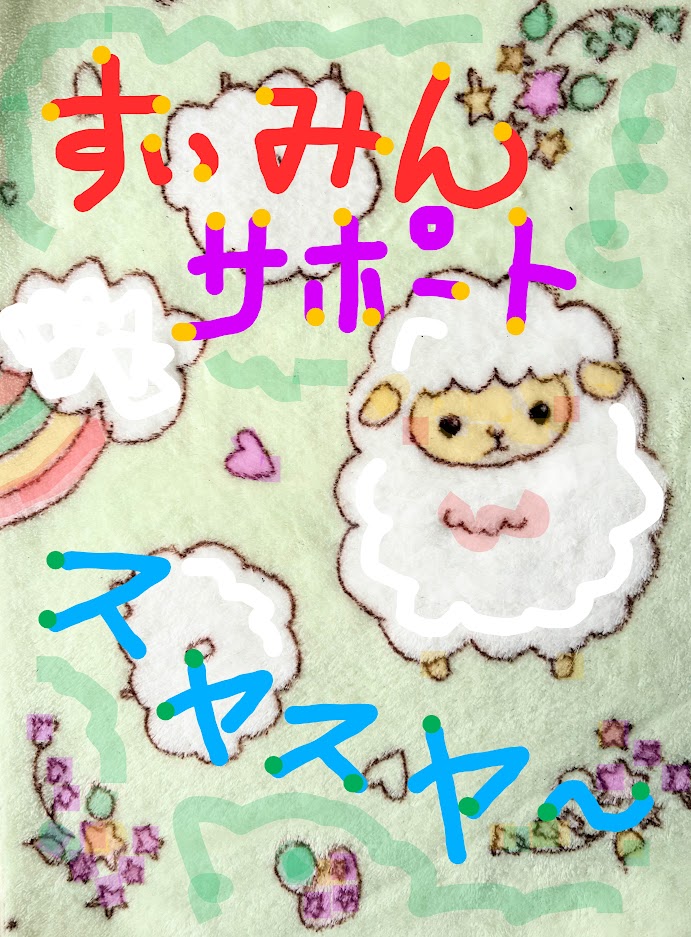



コメント