赤ちゃんの寝顔は、ババやママの一日の疲れを癒してくれますね。
でも、病気でもないのに泣き叫ぶ赤ちゃん
抱っこしてもダメ。
泣き声は近所迷惑。虐待していると間違われたらどうしよう。
なだめて寝かしつけようとするけれど・・・ダメ
パパやママの方が泣きたくなってしまう。
赤ちゃんの眠りは、脳が発達していくためにとっても大切なのです。
スヤスヤ寝ている間に、成長発達するのです。
でも、なかなか寝てくれないという悩みがありますね。
そんな赤ちゃんが寝てくれるためには、練習や習慣づけることが必要なのです。
これを【ねんトレ】・・ねんねんトレーニングといいます。
私は38年間保育者をしていて、たくさんの保護者の方の悩みを聞いてきました。
我が子がなかなか寝てくれないことも問題の一つ。
赤ちゃんが自分の力で眠れるようになるために必要な練習方法や環境づくりについて、
お伝えしましょう!
【ねんトレ】赤ちゃんが眠りやすい音はホワイトノイズ
赤ちゃんがスヤスヤ眠ってくれると、ママやパパはホッとしますね。
赤ちゃんが寝ようとする兆しが見えたら、大きな音をたてないように気をつけたり、玄関に〈赤ちゃんが寝ていますからインターホーンを鳴らさないでください。〉と貼り紙をしたりなど、涙ぐましい努力をされる方もおられます。
個人差は大きく、大家族で育っていると、どんな雑音の中でもすぐに寝る赤ちゃんもいます。
反面、どんなに気をつけてもちょっとした物音で目をさましてしまう赤ちゃんもいます。
とりあえずは、赤ちゃんに眠ってもらうことを考えてみました。
ホワイトノイズは眠りを誘う音
寝かしつけに効果的な音や音楽のことをホワイトノイズと言います。
かつて深夜になると、TVは放映終了となり、画面から映像が消えました。
そして次に現れたのが、砂あらしのような画と音。
この砂あらしの音を聞かせると、ぐずっていた赤ちゃんはすぐに寝てしまうと言われていました。
この砂あらしの音は、赤ちゃんがお母さんの胎内にいた時を思い出させ、安心するからだそうです。
今、この砂あらしの映像を目にすることはなくなりました。
でも身近なところにも、この砂あらしのような音はあるんです。
赤ちゃんの眠りに効果的なファンノイズ
波の音
風の音
雨だれの音
川のせせらぎの音
ママの心音
換気扇の音
チクタクチクタク時計の針の音 など
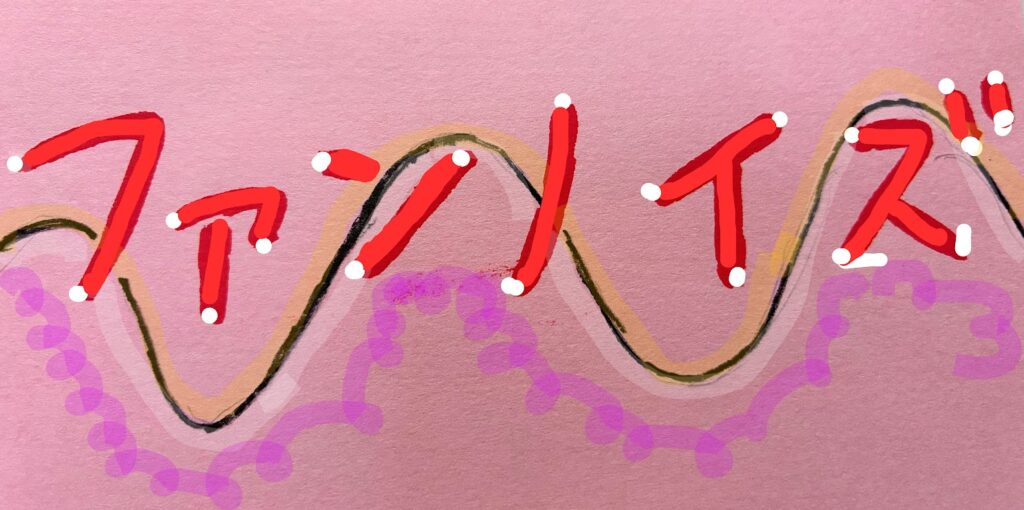
大人でも疲れていて、これらの音を聞いていたら、なんだか眠くなってしいますね。
これらの音は、赤ちゃんの眠りを誘います。
音の波長としたら、大きな波のうねりがゆったりゆったり押し寄せてくる感じですね。
電子ノイズも効果あり
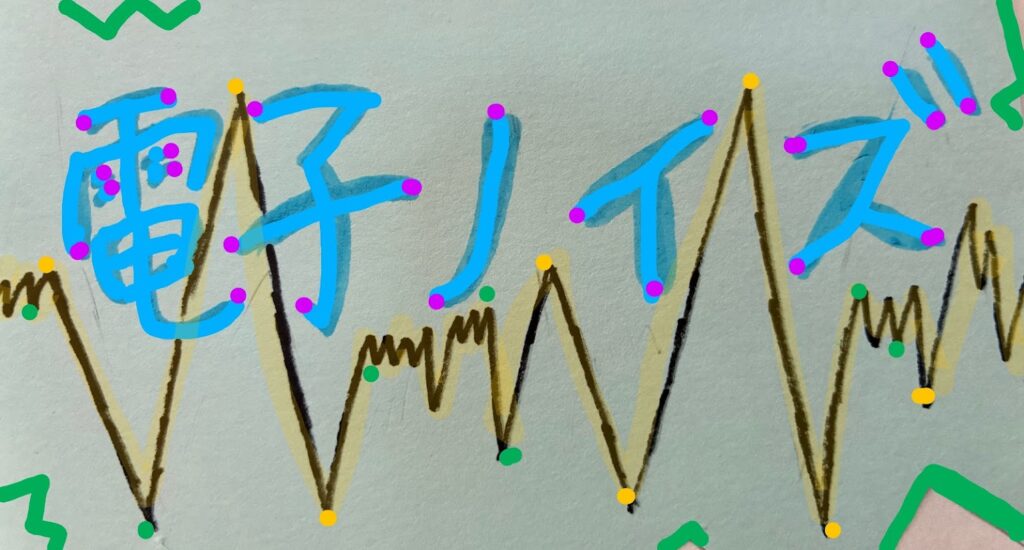
パパが、赤ちゃんの側でパソコンをカチャカチャ
ママが、髪を乾かすためにドライアーをかけている音
お兄ちゃんがゲームを楽しんでいる音
台所の換気扇の音 など
赤ちゃんによっては、電子ノイズであっても寝てしまうことがあります。
なんとなく、ほんと?と思いたいですが・・・
電子の音であっても、リズムが一定のものならば眠りを誘うのです。
ただし、赤ちゃんによって個人差はありますよ。
赤ちゃんの眠りにNGな音
大人でも、これはイライラするという音がありますね。
せっかく落ち着いているのに、突然の大きな物音にびっくりして、目が覚めた!という体験。
テレビやラジオの突然の大きな音
隣接した道から工事の音
窓から聞こえる大勢の大声の話し声
かみなりの音
車のエンジン音 など代表的ですね。
- 突然の大きな音(工事の音 食器を落とす音 ドアのバタン音 大声 叫び声)
- 高い音や鋭い音(インターホン アラーム 目覚まし音)
- ボリュームが大きい音(バラエティ番組やアクション映画 それに反応する人の声)
- 複雑な重なっている音(複数の人の話し声 カフェのような環境音)
【ねんトレ】の方法
【ねんトレ】は「ねんねんトレーニング」のことです。
赤ちゃんが自分の力で眠れるようになるための練習や習慣づけをやってみましょう!

〈ママやパパの願い〉
「毎晩、毎晩、寝てくれるかなぁと心配したり、サポートしなくても
コトンと寝てくれたら、楽なのになぁ」
「夜中に何度も起きると大変!もっと長く寝てくれたらいいなぁ」
「睡眠のリズムがある程度一定になってくれたら、こちらも予定が立てやすいのだけど。赤ちゃんが起きるたびに、家事の手を止めてしまわないといけない。」
【ねんトレ】基本的なステップ
- 環境を整える・・・部屋を暗くしたり静かにしたりする。
しかし、いつもの環境と大きく変えると不安を感じ、逆に眠れなくなることもあります。 - 寝る時間・・・・・同じ時間に寝かせる。
・体に寝ることを覚えさせるのですね。 - 寝る前に、赤ちゃんを興奮させない。
・TVやスマホの光を避ける。
・激しい遊びを避ける。 - 寝かしつけの仕方を見直す。
・抱っこや授乳でいつも寝かしつけていたのならば、少しずつ減らしていく方がいいですね。 - 泣いてもすぐには抱っこしない。
・個人差はありますから無理をしないでいいですが、泣いても少し待って、様子を見守るということも大切です。
それから、必要ならば抱っこして気持ちを落ち着かせましょう。
【ねんトレ】注意すべきこと
・ ねんトレは、寝かせっぱなしにする方法ではない!
ねんねんころのトレーニングだから寝ていて訓練と思いがちですが、赤ちゃんが目を覚ましている時
からの訓練が必要です。
・ 赤ちゃんの性格や家庭の状況に応じて、無理なくやることが大切です。
赤ちゃんの気質が大きく影響します。赤ちゃんの気質は、つまりはママやパパの性格でもあるわけで
す。ねんトレに限らず、育児に対するすべての取組として、ねんトレを考えていきましょう。
・ 家庭環境は、とっても影響が大きいです。
TVで、大家族の中で赤ちゃんを育てている様子を見たことがあります。
あんなに、赤ちゃんを雑に扱っても大丈夫なの?とか、あの賑やかな環境の中でよく眠れるね~と
感心します。赤ちゃんにとっては、日常と変わらない状況が、ねんトレにベストな環境なのかもし
れません。
・ ママやパパが、「今日はがんばれそうだな」と思った時に、少しずつやれば大丈夫です。
赤ちゃんも大人も無理をしないことです。
【ねんトレ】主な方法
- フェードアウト法
赤ちゃんの状況を見ながら、ママやパパが少しずつ寝かしつけのサポートを減らしていく方法 - チェック&コンフェート法
赤ちゃんをベッドに寝かせた後、泣いてもすぐに抱っこしたりせずに、決まった間隔で声掛けや軽いタッチをする。 - ルーティンの固定
毎日同じ時間に同じことをすることで、「眠る時間だ」と体に教えていく方法
【ねんトレ】睡眠の発達段階に応じて
睡眠は、子ども一人一人の気質や家庭環境によって個人差はとっても大きいのです。
これは、大人にとっても同様ですね。
ただ、赤ちゃん(乳児)から子ども(幼児)までの発達段階に応じて、ある程度の睡眠の形は決まっています。
ねんトレをするにあたって、この睡眠状況を知っておくことも大切です。
〈1~3ヶ月・・・生まれたばかり〉
・1日の睡眠時間は、16時間から20時間程度
・1日の大半をうとうとと寝て過ごす。(3~4時間ごとに目覚めと眠りを繰り返す。)
・3~4時間ごとに目覚めと眠りを繰り返す。
・目覚めると泣く。
目が覚めると、やさしく声掛けをするといいです。
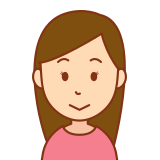
「いい子ね」「そばにいるから、だいじょうぶよ」
〈4~5ヶ月・・・首がすわる〉
・1日の睡眠時間は、15時間程度
・抱っこで寝かせると、布団に移した時に目覚めることがある。
・昼夜の区別がつき始める。
・朝7時頃目覚め、日中は2~3回眠る。
・夜8時頃から朝まで眠るようになる。
少しずつ睡眠のリズムができて、「寝る」「起きる」の区別がついてきます。
起きた時には。着替えさせたり、冷たいタオルで顔を拭いてあげたりして、しっかり目が覚めるようにするといいですね。
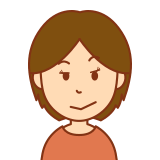
「あら、目が覚めたのね」
「いっぱい寝て気持ちいいね」
〈6~8ヶ月〉
・1日の睡眠時間が、14時間くらいになる。
・寝返りをする。
・眠くなるとぐずったりして眠いサインを出す。
満腹で、オムツも濡れていないのにグズグズは、眠いサインかも。
抱っこしてゆらゆらしたりトントンしてじっくり関わってあげましょう。
安心感を与えてあげるといいですね。
子守唄を歌ってもいいですよ。
それでも眠れないという時は、一度外の空気に触れさせたりして気分転換してから
もう一度ねんねに挑戦!
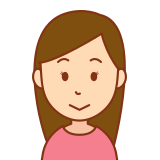
「眠いのね、よしよし、ねんねしようね。」
〈9ヶ月・・・日中活動的になる。〉
・1日の睡眠が午前・午後・夕方の3回になる。
・昼夜の区別がはっきりしてきて、午睡の時間が一定になってくる。
毎日の活動サイクルが一定になるように調整していきましょう。
特に、保育所と家庭がしっかり連絡を取り合って、睡眠のリズムが狂わないようにしたいです。
そのためには、できるだけ毎日同じ時間に寝て起きるという習慣をこの時期からつけていくと
あとあと楽になりますよ。
〈1歳前半・・・生活リズムが安定してくる。〉
・1日の睡眠は、12時間程度(夜の睡眠は9~10時間、午睡を入れると12時間くらい)
・昼間は午前中1回、午後1回の2回の睡眠で十分になってくる。
・食事や遊びの途中でも眠くなると寝てしまうことがある。
・何かを触りながら入眠するなど、寝入り方に個性が出てくる。
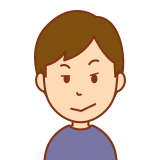
いつも同じタオルケットがないと眠れない。
お気に入りのぬいぐるみが必要・・・
それで心が安定して寝てくれるならば、うれしいですね。
実は、私も子どもの時にそうでした。
ぬいぐるみが汚れてお洗濯した時は、心細くって~(笑)
〈1歳後半〉
・午後1回の睡眠で元気に過ごせるようになる。
・ノンレム睡眠(深い眠りで、脳も休んでいる)割合が増し、熟睡するようになる。
・目を描く、耳をこするなど、眠い時のしぐさが現れる子どももいる。
・途中で目覚めても、ママや保育者などがそばにいることがわかると安心して、また眠る。
・夜、眠る前に「おやすみなさい」。目覚めた時に「おはよう」を言う。
少しずつ、子ども自身が寝る時間を意識できるようにするといいですね。
お風呂に入ったから後は寝る時間だというように、生活の中で寝る時間帯を子どもにもわかるようにしていきましょう。
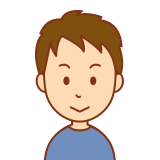
我が家では、寝る前に絵本を読んでいました。
眠くなるような刺激の少ない本を選んでいましたが、我が子が選ぶ時もありました。
絵本を読み終わったら、とりあえず電気を消して、「寝る時間でーす」
これで、子ども自身もうすぐ寝る時間だという心構えができてきてのかな。
睡眠時間のリズムがついていったような気がします。
〈2歳前半・・・日中の運動量が増える。〉
・一般的な睡眠時間は、トータルで11~12時間(午睡は、1~2時間)
・午後寝を意識して、行動できるようになる。
〈2歳後半〉
・友達と一緒に寝ることを喜ぶ。(保育所で)
・一人でも眠れるようになってくる。
・午後一回の睡眠で、体力の回復ができるようになる。
・朝の光を浴びることで、生活リズムが安定してくる。
・遊びも活発になってきたため、遊びすぎたり興奮しすぎたりすると、逆に寝つきが悪くなったり
熟睡できずに途中で目覚めたりする。
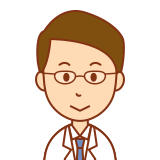
3歳児以上は、保育所や幼稚園に通園する幼児も増えますね。
赤ちゃんの時は、レム睡眠が多く、
これは脳の機能が発達することに大きな影響を与えていました。
幼児になると、保育所や幼稚園でしっかり遊んで疲れて、夜は爆睡!
従って
ノンレム睡眠の割合が増えてきますね。
今度は、脳だけでなく
体の成長ホルモンに大きく影響していきますよ。
園との連携をとりながら、しっかり眠らせてあげましょう!
〈3歳〉
・眠くなると自分から「眠い」という子もいる。
・午睡から覚めても、まだ眠くて泣くことがある。
・家では、一晩中ぐっすりと眠るようになる。

眠れない時に読んであげる絵本、たくさんありますね~
私は、せなけいこさんの赤ちゃん絵本「ねないこだあれ」をよく読んでいましたよ。
〈4歳〉
・午睡をしない子がいる。
・午睡の準備や片付けができる。
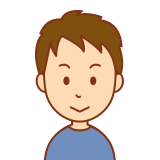
自分の生活時間がかなり決まってきましたね。
朝起きたら~する。
幼稚園に行く。
晩御飯を食べたら~をする。
歯磨きしたら~
こんな生活のリズムを、ルーティンとして体に刻んでいけば、
ベットに入ったら【寝る】となるかもしれませんね。
〈5歳〉
・午睡をしなくなる子が多くなる。
・夜眠る前の支度が、自分でできるようになる。

活動量も多くなるから、お腹がすいたら眠れないよね。
だからといって、食べ過ぎてもダメ。
活動と食事量の関係も考えたいわね。
〈6歳〉
・寝ている時のおもらしをしなくなっている。
・早寝・早起きの意味がわかる。
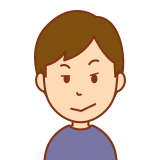
寝る前のゲームはダメ。
お父さんだって、パソコンを寝る前までしていたら、寝られなくなる!
【ねんトレ】赤ちゃんとの関わり方
睡眠や食欲などは、本当に個人差が大きいです。
しかし、うまくいかないからといって、決してお子さんに問題があるわけではありません。
〇一人一人の生活のリズムをつかみましょう!
赤ちゃんの自然な要求が優先です。
眠たい時には、しっかり寝かせるようにしましょう。
授乳の時間だからといって、寝ているのを起こしてまでミルクを飲ませる必要はありません。
〇目覚めた時には、不安にならないようにしてあげましょう。
眠りが浅い時には、ちょっとした物音で起きてしまうことがあります。
でも、そばに誰かがいる時には、やさしく声を掛けてあげたり抱き上げてあげたりして
ください。安心したら、また眠ります。
〇眠たいのに眠れない、ぐずぐず~の理由を考えてみましょう。
具合は悪くないですか?
おなかがすいていない?
オムツが濡れていない?
環境が大きく変わっていない?
それらの原因を取り除いても、ダメ?
ママにどこか不安がある?
音楽をかけたりして、お母さん自身が気持ちをリフレッシュして、一対一でゆっくり関わって
みましょう。
〇体に「寝る」「起きる」のメリハリのリズムをつけてあげましょう。
睡眠のリズムをつけるには、太陽の光の力は大きいですよ。
日中に、太陽の日差しを浴びて、活動的に(赤ちゃんなりの動き・・・手足を動かしたり、
マッサージしてあげたり)過ごすことで、心地よい疲労感が与えられますね。
そうすれば、自然に夜には眠りにつけますよ。
また、起きた時の声掛けは「起きたね!いい子ね!」と明るく。そして着替えや体を拭くなどして
体や脳が起きるようなサポートをしてあげてくださいね。
寝る時は、逆です。「ねんね~」ゆったりゆっくりの声掛けです。
【ねんトレ】うまくいかない
赤ちゃんが寝ないと焦りますね。
確かに泣き声が近所迷惑になりそうだとか、仕事で疲れているパパから「静かにさせろ!」と叱られたりしたら、ママの方が泣きたくなる。
でも、ママの焦りが赤ちゃんに伝わって、もっと赤ちゃんは眠らなくなるのです。
赤ちゃんが眠らないという母親の不安感が、赤ちゃんにつたわりさらに不眠状態になる恐れがあります。
ママは、気持ちを切り替えてみましょう。
ママやパパの気持ちを切り替える方法
これは、大人がなかなか眠れない時にも通じることです。
〈光〉〈音〉〈香〉この3つを生活の中に取り入れてみましょう。
- ぬるめのお風呂でリラックスする。
大人でも、寝る前直前のぬるめのお風呂が質のいい睡眠に有効であることは知られていますね。
赤ちゃんだって、泣いて体が汗っぽくなっていたら不快ですね。
温かいタオルで、やさしく拭いてあげましょう。 - 朝の光をしっかり浴びさせ、夜の光を避ける。
体に「寝る」「起きる」のリズムを付けさせることですね。
上記の発達段階に応じた方法でも記述しています。
ある家庭では、「9時になったら部屋の電気を消します。その代わり、朝4時か5時には起きます。」とのこと、参考までに。 - アロマテラピーを取り入れる。
植物の花や葉などから抽出したエッセンスが、たくさん出回っていますね。
ただし、香りによっては、体を活性化(目覚めさせる)ものもありますから、要注意です。
体のリラックス状態にしてくれる
〈眠りに誘う香り〉は
ラベンダー・ローズウッド・ビターオレンジ などです。
触れ合いをいい思い出に
確かに、今は苦しい時もある。
でもこんな会話が聞こえてきましたよ。
赤ちゃんが眠らなかった経験があるママ2人の会話
A「うちの子は、なかなか眠らなかったわ。」
「原因はわからない。どんなに部屋を静かにしてやっても・・・」
「だから、夜中であっても外に抱っこして、連れ出していたの。」
B「そうそう、うちの子もなかなか眠らなくて苦労したわ。」
「私も気分を変えようと、外に出て、我が子と一緒にお星さまを数えてた!」
「夜中の3時!」
「そうしたら、向こうから新聞配達が来るのが見えて、まさかこんな姿が見られたらと
慌てて物陰に隠れたり・・・(笑)」
A「ほんとね。まさかまさか~そんな夜中に赤ちゃんを抱っこした女の人に出会うなんて、、
新聞配達の人だってビックリされるよね~」
B「でも、我が子が大きくなった今、あの頃が懐かしいのよね。」
「我が子とあんなに密な時間を過ごせるなんて!我が子は私にしっかり抱っこされて」
A・B 「ママとしての至福の時!」
A「それに、あんなに夜空の星を眺めることなんて、なかなかないよね~」
B「我が子が寝らなかったからこそ、私は流星群だって見ることができたわ。」
A「私たち、我が子が寝なかったからこそ、他の人にはできない経験もしたということね。」
いつかは、今、赤ちゃんが眠らないという辛さから抜け出します。
AママとBママの2人にとっては、子育ての中の懐かしい思い出に変わっていました。
まとめ
赤ちゃんの睡眠は、脳機能の発達に大きな影響がありますね。
それだけに、たっぷりと寝てもらいたいものです。
しかし、最近の環境を考えたら、赤ちゃんの睡眠を邪魔してしまうものもたくさんあります。
もっとも、一人一人の気質、家庭環境、パパやママの性格も大きく影響します。
そういうものを全部ひっくるめて、赤ちゃんがスヤスヤと寝てくれるには、やはり睡眠の訓練が必要なんです。
【ねんトレ】のさまざまな方法をお伝えしてきました。
家庭の状況を考えて、いろいろやってみましょう!
まずは、眠りを誘うホワイトノイズをたくさん見つけてくださいね。
ただ、赤ちゃんが寝ないからといって、あせらないでください。
2人のお母さんの経験談にもありますが、
寝ない赤ちゃんと過ごす時間を、親子の触れ合いの時間だと考えて、一緒に楽しみませんか?
長い人生の中で、この子育ての時間は、あっという間に過ぎてしまいます。
辛かった思いも懐かしさに変わってきますよ。
ママ、星空を眺めて過ごしてみませんか?
頑張ってください!!



コメント