弟が生まれると知った時には大喜びした6歳男児。
自分の事はほとんどできるようになっていたし、きっといいお兄ちゃんになってくれるだろうと期待していた。
しかし、弟の誕生からしばらくして食欲がなくなり、いつものような笑顔が消えた!
幼稚園にも行かないと言い出した。
パパやママは、そんなお子さんの姿に戸惑ったことでしょう。
愛情はたっぷり注いでいるはずなのに、、、どうして?
なんとか以前の元気な姿に戻ってほしいと思いますね。
妹や弟が生まれたら、きっといいお兄ちゃんやお姉ちゃんになってくれるだろうと思っていたのに、
現実は上の子どもに予想外の行動が出て、大きな悩みになってしまいました。
程度に差はあれど、赤ちゃんのようにわがままを言ったり、食欲が落ちたり、おもらしをしたりするのは赤ちゃん返りという行動なのです。
決して特別の問題行動ではありません。
子どもが成長していく上で、よくある行動であり、成長の一つの姿だと言えます。
私は38年間幼稚園に勤めていて、このようなパパやママの悩みをたくさん聞いてきました。
お子さんの心の声をしっかり聞いて、対応すれば大丈夫です。
お子さんが元気になり、元の笑顔を取り戻すような関わり方についてお教えしましょう!
いつの間にか、お子さんは赤ちゃん返りの坂を越えて、グーンとお兄ちゃんらしく(お姉ちゃんらしく)成長していることでしょう。
【育児の悩み】赤ちゃん返りは、成長の一つの姿
お子さんの成長は、本当にうれしいものですよね。
昨日できなかったことが、今日はできるようになっている。
お子さんも、それがうれしくて「ママ、見て、見て!」と得意そうな表情で披露してくれる。
どんなに仕事で疲れていても、お子さんの成長が目に見えている時には、子育ての喜びを味わえるものですね。
【育児の悩み】赤ちゃん返りとは?
お子さんが急に問題行動を起こすようになったら、びっくりしますよね。
自分の力で何でもしようとがんばっていたはずなのに・・・急に「ママ~して~」と半泣きの甘えた声
トイレの失敗もほとんどなくなっていたのに・・・まさか!おねしょ?
ちょっとのことで泣きそうになったり、グズグズしたりして、「抱っこ~」
自分一人でできないことがあると癇癪を起して「ぎゃ~!」「できない」
パパやママの姿が見えないと探し回って・・・挙句の果てに大泣き
生後間もない弟に対して・・・「○○くんは、嫌い!」
夜中に急に起きて、夜泣き!
人がいるスーパーなどで、急に赤ちゃん言葉で話し始め、わがままになる。
運動量が減っているわけではないのに・・・・パタッと食事量が減ってしまった。
何より、以前のような生き生きとした子どもらしい表情が消えた。
お子さんによって、赤ちゃん返りの姿は様々です。
弟や妹ができたことによる心の揺れが、目に見えぬストレスや様々な問題行動となって表れたのです。
【育児の悩み】赤ちゃん返りがどうして起きた?(子どもの心の声)
なぜ、赤ちゃん返りが起こったのでしょうか?
このことを考えることで、これからの対応策が見えてきます。
1 兄弟が生まれたことで起こる心理的変化(寂しさ・嫉妬・兄や姉になったことへの不安)
おそらく弟が生まれるまでは、お子さんは自分中心の生活だったのでしょう。
親としたら、我が子のどちらもかわいい。決して差別しているわけではない。
しかし・・・
〈お子さんの心の声〉
大好きなおじいちゃんやおばあちゃんが遊びに来た時に一番初めに声を掛けたのは、僕よりも
弟の方だった。
これまでは、僕に対して「大きくなったな~」と一番先に言って喜んでくれたのに。
僕よりも弟のところに行って「かわいいな~パパにそっくりだ」と弟のほっぺを笑顔で触っていた。
なんだか、寂しい。
〈お子さんの心の声〉
幼稚園から帰った時、僕はすぐに幼稚園で作ったおもちゃをママに見せた。
ちょうどママは、弟にミルクをあげる準備をするところだった。
「ママ、見て~僕が作ったんだよ。幼稚園の先生がよくできたねって、ほめてくれたよ。」
ママは、「ほんとね。上手~」とほめてくれた。
でも、ママは「ちょっと待ってね。ミルクあげてからね。」と言って、弟の所に行ってしまった。
以前のママだったら、「すごい!ここんところ、がんばったんだね。」と作品を見て、大切そうにして
「パパが帰ったら見せてあげようね。」とリビングの棚に飾ってくれた。
せっかく頑張って作ったのに、なんだかがっかりだな。
2 6歳という年齢による成長の自覚と不安
6歳と言えば、幼稚園では年長組でみんなから頼られることも多いです。
来年、小学生になるための準備も少しずつ進んでいて、お子さん自身成長の自覚と喜びを大きく感じているはずです。
しかし、やっぱりまだ6歳です。
しようと思っても思うようにできないことも多いし、やったことに対して満足いかなかったりすることもあるのです。
そんな時、幼稚園や保育所では先生がサポートしてくれ、ポジティブな取り組みができるようにしてくれています。
家庭でも、パパやママが先生と同じようにに関わってはおられることでしょう。
でも家事や仕事に追われている時には、十分にできないことがあるのも当然です。
さらに下のお子さんが生まれてからは、上のお子さんにかまってあげる時間が少なくなったのではないでしょうか?
そのような環境の変化を敏感に感じ取って、お子さんは心がとっても揺れているのです。
〈お子さんの心の声〉
弟ができてから、なんだかママを取られてしまったみたい。
ママが手伝わなくても、僕は頑張ってやれるけど、時々不安になる。
「僕、だいしょうぶかなぁ~」
「本当にお兄ちゃんになれるのかなぁ」
「こんな僕、来年一年生になれるのかなぁ」
やっぱり困った時には、ママやパパにそばにいてほしいな。
【育児の悩み】赤ちゃん返りの対処法
もし、お子さんが突然赤ちゃん返りしたら、慌てますよね。
特に、食欲不振や睡眠不足はお子さんの成長に大きく影響し、病気にもなりかねない。
栄養不足になったら大変だと、小児科に行って点滴でもしてもらおうかと考えたり、
どこか相談をするところはないかと探してみる。
子どもの健やかな成長を願う親ならば、当然のことです。
【育児の悩み】親の対応
1 お子さんの問題行動を否定しない。
お子さんなりに一生懸命に頑張っているけれど、どうしようもない姿なんです。
お子さんだって、本当はいいお兄ちゃん(お姉ちゃん)になりたいのです。
だけど心が言うことを聞かず、揺れているのです。
そんな時に「お兄ちゃんでしょ!しっかりしてちょうだい!!」
「あなたはもう大きいから、一人でできるわよ。」などと叱咤激励してしまうと、当然、お子さんの
ストレスは溜まってきます。
そのストレスがいっぱいになってきた時に、赤ちゃん返りという問題行動が出現してしまうのです。
お子さんができないことを指摘するよりも、頑張っている姿・お兄ちゃんになろうとしている姿を認めてあげましょう。
きっと、お子さんは自分のことを見ていてくれたと安心し、失敗しても次に頑張るよという気持ちになってくれるでしょう。
大人だって同じです。
失敗を責められるよりも、ちょっとでもできたことを認められる方がやる気がでますよね。
2 言葉で愛情を伝える。
お子さんが頑張ったことをしっかり見て、「ママはとっても助かった、ありがとう!」
「こんなことまでできるようになったんだね。ママは、うれしいよ。」ときちんとどこが助かったのかを伝えてあげましょう。
できれば、上のお子さんができるような仕事を与えて(とっても簡単な仕事でいいのです。でも、それをすることでママが助かるようなこと)
できてもできなくても、やってくれたことを認めてあげましょう。
上のお子さんも家族の一員であり、とっても必要な存在であることに気づかせていきたいですね。
3 上のお子さんとの特別な時間を作ってあげる。
ママは、下のお子さんの世話で忙しいでしょう。
でも少しの時間でいいのです。
寝る前のわずかな時間でもいいのです。
「今日は、赤ちゃんのお世話でママが忙しい時に、テーブルを拭いてくれたね。」
「リビングが散らかっていたけれど、おもちゃ箱にきちんと片付けてくれたのね。ママは気持ちよくなったわ。ありがとう!」
「お兄ちゃんになって頑張ってくれたから、ママから大好き好き~のプレゼントしてあげる!」
寝る前に、心が穏やかになるひと時です。
お子さんは、1日のストレスも取れてぐっすりと寝てくれることでしょう。
時には、「ママとの内緒だよ。」とこっそりおやつを食べてみたり、秘密の時間だと称して、思いっきり抱っこやハグしてあげる。
子どもは、秘密とか内緒とかいう言葉が大好きです。
ママと自分だけの秘密の時間を共有できたお子さんは、ママやパパに愛されているという事が分かり、
ルンルン気分になれます。
4 食べることを無理強いしない
子どもの食べる意欲はその子の生きる力のバロメーターです。
子どもがパクパク食べる姿をみれば、親としてはうれしいです。
健康ならば、たとえ少しくらいその子が悪さしても、許してしまう。
コロナ禍では、給食やお弁当の時間には、子ども同士対面することなく、無言で食べることを強要しました。そんな食事では、おいしくなく、当然子どもの食事量も減りました。
やはり、楽しい雰囲気の中で食べることが一番ですね。
マナーを教えることはもちろん大切です。
好き嫌いなく何でも食べることは大切です。
でも、それはお子さんが自分で食べようとすることができるようになってからですね。
【育児の悩み】相談コーナー

ママとの大切な時間って?(保育者に悩み相談)
ママ「先生、最近、うちのM男はご飯を食べなくなって、、、
このままだったら、病気になってしまうのではないかと心配なんです。」
Y先生「幼稚園では給食を食べてはいますが、やはり以前に比べちょっと少食になっていますね。」
Y先生「健康診断では異常はありませんでしたね。何か、原因にお心当たりはありますか?」
ママ「どうも、弟が生まれてから少食になったような気がするのです。」
「弟が生まれた時には、とっても喜んでいたのですが・・どうしたんでしょうか?」
Y先生「なるほどね。M男くんが元気がなくなっていた原因は、それですね!」
ママ「M男は、病気ですか?」
Y先生「赤ちゃん返りという病気ですよ!」
ママ「??」
Y先生「正確には病気ではありませんから、心配はいりませんよ。」
Y先生「下に弟や妹が生まれたら、うれしいのだけど、大好きなママを取られてしまったような気持ちになってしまうのです。これまで、ご両親に愛情たっぷりに育てられたお子さんに多く、一時的な問題だから解決しますよ。」
Y先生「この気持ちは、ほとんどのお子さんが、大なり小なり経験します。」
ママ「弟が生まれても、それまでと変わらないように精いっぱいにM男には接してきましたが、私が気付かないところでM男は寂しさを感じていたのですね。」

ママ「それでは、これからどのようにしたらいいでしょうか?」
Y先生「M男くんと二人だけの特別の時間をつくってみませんか?」
ママ「先生、それは無理です。下の子をおいていくわけにはいきません!」
Y先生「特別な時間といっても、一日中、ディスニ―ランドで遊んで来たらというのではありませんよ。(笑)」
Y先生「1時間くらいだったら、弟くんを誰かに見てもらって、その間にM男くんとお出かけはできませんか?近くの公園でいいのです。」
Y先生「M男くんには、今からママと秘密の場所に遊びに行こう!ひょっとしたら、悪者が出てくるかもしれないから、その時にはママを助けてくれる?と言ってね。」
Y先生「お腹が空いていたら、力が出ないから、今からおむすび作って持っていこうよ!」
Y先生「きっと、この提案にはM男くんはびっくりしますよ。」
ママ「弟も連れていくの?と聞かれたら?」
Y先生「弟はまだ小さいから、悪者が出てきてもママを助けてはくれないと思う。
ママは、M男くんと二人だけで行きたいのと話すのです。」
Y先生「これで、M男くんは、ママに頼られているという喜びや自信が芽生えてくると思いますよ」

ママ「食欲不振については、どうしたらいいでしょうか?」
Y先生「今は食べなくても、自信がついてきたら、少しずつでも食べてくれるようになりますよ。」
ママ「それならば、うれしいですが・・・」
Y先生「まだ、ご心配ですよね。初めてのことですからね。」
Y先生「人間、どんなことが起きても食べることができていると安心です。
私たちも子どもの食欲がどのくらいかを、生きる力のバロメーターにすることがありますから。」
ママ「M男が、生きる力をどんどんつけていくような方法を教えてください。」
Y先生「決して食べることを無理強いしてはダメですよ。M男くんが自分から食べたくなるような雰囲気が大切です。」
ママ「雰囲気ですね。」
Y先生「まずはママと二人でお出かけする時に、一緒におむすび弁当でも作られたらどうですか?」
Y先生「ママと一緒にお出かけ、それだけでもうれしいし、加えてお弁当までもっていくなんて遠足にいくみたい。M男くんは喜びますよ。」
Y先生「おかずなんていらない。おむすびに卵焼きだけでもいい。ママと自分の作ったいろいろな形のおむすびは、公園で食べたらきっとおいしくて、食欲がでてくることでしょう。」
【育児の悩み】赤ちゃん返りがなかなか良くならない時
お子さんとの特別な時間をつくったり、ママはきっと赤ちゃん返りの行動を改善しようと頑張っているはず。
でも個人差や家庭環境の違いがあるから、これが正解だという対処方法はないのです。
Aちゃんには、この方法でやってみたらうまくいったとしても、Bちゃんには通用しないこともあります。
でも、がっかりしないでください。
もう少し、対処方法を考えてみましょう。
食欲を取り戻すための工夫
1 安心感を与える
・ 弟が生まれたことでママを取られた~寂しいという気持ちに対しては
→ スキンシップを増やしてみてください。
抱っこする・手をつなぐ・膝に乗せる・膝に乗せて絵本を読むなどママの肌のあたたかさが、お子さんの心をほぐしてくれますよ。
パパとママの真ん中に手を繋いで、ブランコなどもいいですね。
自分がいかに大切に、愛されているか分かってくれるでしょう。
・ 弟に対して、嫉妬のような感情をもっているような時には
→ 『赤ちゃんだった頃の話』をしてみましょう。
お子さんが赤ちゃんだった頃(弟と同じ大きさの頃)の写真や動画などを見て、今の弟と同じくらいにパパやママはかわいいと思っていたことなどを伝えてあげると、自分も大切にされていたことを実感してくれるでしょう。
・ なかなかママの言葉を信じてくれないような時には
→ 寝る前や食事中、ふとしたタイミングで愛情を言葉にして表現することは大切です。
行動で分かってくれると思っていても・・・幸せは態度で示さないといけませんね(笑)
「ママが大好きなM男ちゃん!おはよう」
「パパが大好きなM男ちゃん!今日もいっぱい遊ぼうね」というように声を掛けると、パパやママはいつも僕のことを思っていてくれるんだと、充足感に満たされますね。
2 食事の時間を楽しくする。
・ 一緒に料理をする。
「今日は、M男くんの好きな物を一緒に作ろうね。」と誘って、できるところ(味付けや盛り付けなど)を任せると、自分がママと一緒に作ったんだと料理に関心が高まり、自然に食べることになるでしょう。
・ 赤ちゃん風メニューにする。
弟がうらやましいM男くんなのだから、「今日は、M男くんも弟と同じ献立にしたわよ。」
M男くんのメニューも、離乳食であったり、哺乳瓶に入ったミルクであったり。
果たしてM男くんは食べたでしょうか?
弟と同じ扱いに、なんだか甘やかしてもらって喜ぶかもしれません。
逆に、「えー!僕はこんなものより卵焼きやウインナーの方がいい。」と訴えるかもしれませんね。
つまり、弟のメニューと自分のものを比べることで、自分は弟とは違う!大きいんだ!お兄ちゃんなんだ!と自覚してくれるかもしれませんね。
【育児の悩み】相談できる専門機関
赤ちゃん返りは、成長の一過程です。
発達の一つの姿とも言えます。
しかし、赤ちゃん返りが長引くと、親子関係にひずみができたり、家庭の雰囲気が壊れたりするかも。
ママやパパのストレスが大きくなっては大変です。
1 子育て支援センター・児童館
・地域の子育て支援拠点として、保育士や子育てアドバイザーが常駐していることが多いです。
・赤ちゃん返りの悩みばかりでなく、育児の不安を気軽に話せる場です。
・認定こども園に併設しているところも多く、子どもたちが生活している生の姿を見学できます。
2 保健センター(市町村の保健所)
・保健師や心理士が在籍していて、発達や心の問題について相談できます。
・定期健診のばでも相談可能です。
・必要に応じて専門機関を紹介してくれます、
3 小児科・児童精神科
・食欲不振や睡眠障害など、身体的な症状がある場合は、まずかかりつけのお医者さんに相談するといいですね。
・心の問題が疑われる場合は、児童精神科や発達外来のある病院が適しています。
4 臨床心理士・公認心理師によるカウンセリング
・子どもの行動の背景にある心理的な要因を専門的に分析してくれます。
・親子関係の改善や、親自身の不安へのサポートも可能です。
5 教育相談所・スクールカウンセラー(就学児の場合)
・幼稚園や小学校に通っている場合は、教育委員会の相談窓口やスクールカウンセラーも利用できますよ。
6 地域の市報や『こども医療ガイド』(東京都)で、調べることもできますよ。
頑張ってください。
【育児の悩み】相談するタイミング
まずは、家庭でもできる環境や雰囲気づくりから取り組んでみてくださいね。
どうしようもなくなったら専門機関に!です。
・ 赤ちゃん返りが半年以上続いている。
・ 食欲不振や夜泣きなどで、生活に支障をきたしている。
・ 他の子どもや赤ちゃんに攻撃的な姿を見せ始めた。
・ 親が育児に対して強いストレスや不安を感じている。
まとめ
順調に成長していた我が子が、下に弟や妹が生まれた途端に問題行動を起こしたら、パパやママは本当にびっくりしますよね。
兄弟が増えて、お家は賑やかに楽しくなると期待していたはずなのに、予想外の上の子どもの行動に悩んでしまう。
でも赤ちゃん返りは、決して悪い事ではありません。
成長発達の一つの姿なんです。
運動選手が、走り幅跳びや高跳びで大きく飛躍する前に、一歩後に下がってからダッシュするところを見たことがありますか?
それと同じです。ちょっと下がってこそ弾みがついて、大きく飛躍できるのです。
赤ちゃん返りは、『心の成長のサイン』と捉えたらいかがでしょうか?
ただ現実問題として、パパやママの不安やストレスはあるでしょう。
赤ちゃん返りは「愛されたい」「注目されたい」という気持ちのサインです。
それまでは、お子さん自身気も付かなかったことかもしれません。
それがどういう行動であれ、自己主張できるようになってきたということは、一つの成長です。
焦らずに、お子さんの心が成長しているのだと思って、お子さんの心に寄り添ってあげてください。
今一度、親子の関係や家庭環境の在り方を見直すいい機会にもなります。
パパやママの愛情という栄養を、お子さんの心にたっぷり与えてあげてください。
気が付けば、食欲不振はどこかに。
この赤ちゃん返りを乗り越えた時には、お子さんは大きく成長しているのですよ。
パパやママも楽しんで赤ちゃん返りを乗り越えましょう。
頑張ってくださいね。
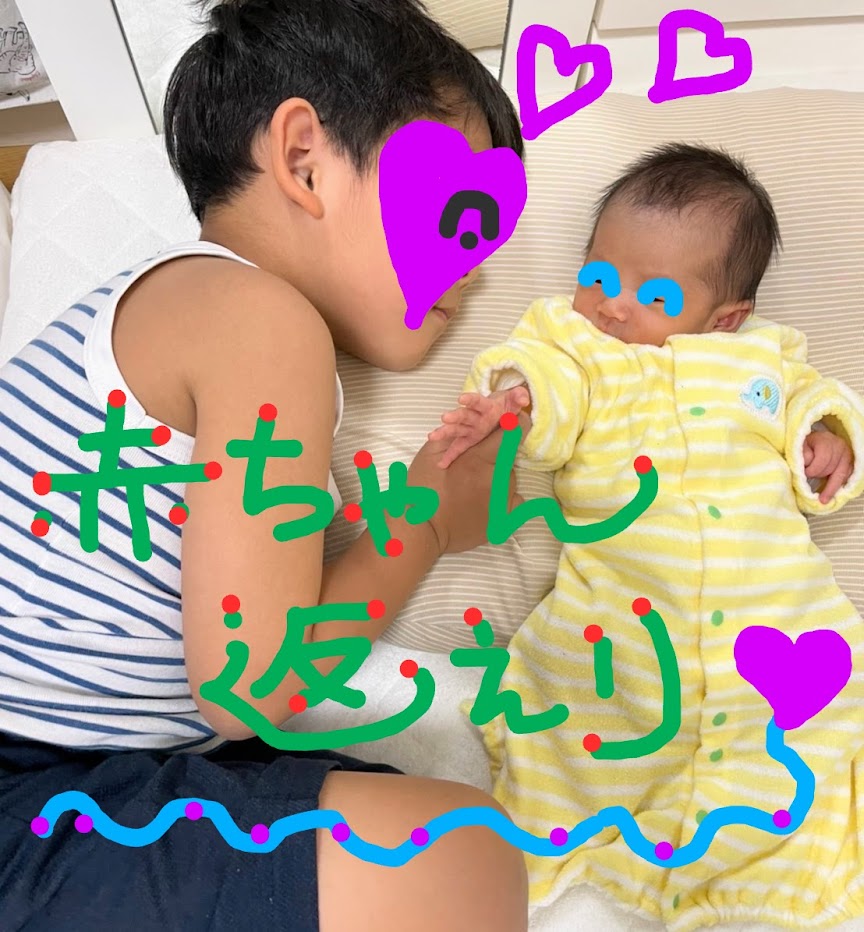
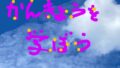

コメント