可愛がっていたペットが死んだ時は、かなしい。
大人でもペットロスになって、何日もご飯が喉を通らないという人がいます。
子どもは、ペットや生き物の死をどのようにとらえているのでしょうか?
ペットが死んだ時に泣き止まない子どもがいます。
ペットのお墓に手を合わせ、お花を飾る子どももいます。
大切にしていたペットが死んだ時、パパやママは子どもにどのように話をしていけばいいでしょうか?
私は38年間幼稚園で保育していて、たくさんの飼育物の死に子どもと共に向き合ってきました。
【ペット(生き物)の死】にどのように対応すべきか、またその出来事を通して、
子どもの心に何を育てていくかをお伝えしたいと思います。
お盆や秋のお彼岸もすぐです。
今、ペットが元気でも、命の大切さや生き物への愛情について考えるいいチャンスです!
【ペットとのお別れ】ペットの死と向き合うために
ペットと言っても、いつも生活を共にしている犬や猫、ウサギ、ハムスター、小鳥
また、草原や川で捕まえた虫やザリガニ、植木鉢の陰にいた丸虫など様々です。
子どもにとってはバッタや丸虫などでも、犬や猫などと変わらず、大切なお友達。
虫かごに入れて餌をやったり、話しかけたりしてかわいがる姿が見られます。
子どもがかわいがる生き物すべて、ペットですね。
ペットの死は、生き物の種類や大きさとは関係なく、
いかに生活を共にしたかという思入れによって大きく違い、子どもの悲しみ方にも差があります。
また年齢や発達段階によって、死に対する受け止めは様々ですから、お子さんの状況に応じて対応していきたいですね。

【ペットとのお別れ】ペットの死をごまかさない
ペットの死をどのように伝えるか?
死んだことをごまかさないでください。
「誰かが連れて行った。」と嘘をつくこともよくありません。
ペットがいなくなったことをいつまでも考えて、むしろ立ち直りが遅くなります。
年齢によっては、「お星さまになったのよ」とか「虹を渡っていった」など話すことで悲しみが和らぐならば、それもいいでしょう。
大切にしていたペットがいなくなったということで混乱しないように、
具体的にもう会うことはできないのだということを認識させていきましょう。
【ペットとのお別れ】ペットの死を共有しよう
お子さんの世話していた姿を思い出すと、パパやママも辛くなりますね。
「悲しいね」とか「辛いね」など声をかけて、お子さんに寄り添ってあげましょう。
大人だから、子どもと同じように泣いたらおかしいということはありませんよ。
一緒に悲しんであげるといいです。
子どもを元気づけようと、無理に明るく振る舞う必要はありません。
大人も同じように涙を流していることを見たお子さんは、きっと、悲しい時には素直に泣いていいんだと思い、自分の感情を素直に表現するようになります。
このことが、悲しみを和らげることに繋がるのです。

【ペットとのお別れ】お別れ儀式をしよう!
ペットの死を認識するためには、きちんと儀式をした方がいいですね。
もっともお子さんが儀式に参加することを望まないのならば、無理強いはしません。
また、幼稚園・保育所・小学校に行っている間に行う場合は、必要に応じて、休んで葬儀に参加してもいいと思います。
子どもがどうしたいのかを一番に尊重してあげましょう。
幼稚園でのお別れの儀式
〈ある幼稚園でのこと・・・エピソード〉
子どもたちがとっても大切にしていたウサギのチッピが死んでしまいました。
とっても賢いウサギで子どもたちの側で一緒に絵本を見たり、いつも子どもたちが遊ぶ場所には、
チッピの姿がありました。
子ウサギの時にカラスにつつかれて片目でしたが、子どもたちとチッピはとても仲良しでした。
しかし高齢になったチッピ、少しずつ弱ってきた姿を見ていて、子どもたちは心配していました。
死の場面に子どもは立ち合いませんでしたが、朝、登園してきた子どもたちは、
先生からチッピの死を知らされ、顔を見に来ました。
それから、チッピのお墓を作ってあげようということになりました。
園庭の片隅に穴を掘り、草のクッションの上にチッピを寝かせました。
一人ずつお花を手に持ち、チッピのお墓に入れていきました。
子どもながら「チッピ、遊んでくれてありがとう」
「チッピ、お星さまになっても見ていてね。」と、それぞれ考えた言葉でチッピに語り掛けたのです。
死に出会ったことが初めての子どももいます。
この幼稚園では飼育物の死を隠さずに、子どもと一緒に向き合うようにしました。
年齢の小さい子どもは、大きいクラスの子どもたちの姿を見ながら、チッピとのお別れができました。
その後、チッピとの楽しかった生活の様子を感謝の気持ちをこめて、みんなで絵本作りをしました。
いつまでもチッピとの思い出は、子どもたちの心に残ることになったのです。
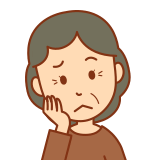
ちょっと怖ーいお話(エピソード)
幼稚園で飼育していた小鳥が死んでしまいました。
子どもたちも毎日世話をして可愛がっていたため、みんなでお墓をつくってあげました。
「ピーちゃん、天国にいってね。」と手を合わせた子どもたちです。
翌日、お花をあげようとお墓に行くと、3歳児M君がお墓を掘り返しています。
A先生はびっくり!
Mちゃんが悪さをしているかと思い、大きな声を出しました。
Mちゃんは、「ピーちゃんは、まだお星さまになっていなかったよ」と答えました。
そうです。
お墓にピーちゃんを入れる時に、A先生は子どもたちに
「ピーちゃんは、死んで天国に行くけれど、お星さまになって
みんなを見ていてくれるからね」と話していたのです。
Mちゃんは、先生の言葉を信じていました。
そして翌日お墓を掘って、ピーちゃんが本当に天国にいったかどうかを確かめたのです。
幼児にはよくある事例なんです。
お墓の儀式をする時には、死んで天国にいくけれど「途中で見たらダメよ。
ゆっくり眠らせてあげようね。」と声を掛けておく必要がありますね。
ペットとのおわかれの言葉
子どもたちに、ベットの死を認識させながらも、むしろペットと生活した大切な時間が思い出になるような言葉がけをしてやりたいですね。
お子さんの年齢や発達段階、性格に合わせて声をかけてあげましょう。
パパやママも、悲しさや寂しさはお子さんと同じだという共感の気持ちで寄り添ってあげましょう。
〈おわかれの言葉の例〉
・「〇〇ちゃんは、もう死んで動かなくなったの。だから、私たちと一緒に遊んだり、ご飯を食べたりすることもなくなったのよ。ちょっとさみしいね。
でも、○○ちゃんは、Mくんといっぱい遊んで楽しかったよ~と言ってるよ。
一緒にお散歩した時の写真を飾ってあげようね。
そうしたら、いつまでもMくんの心の中に○○ちゃんはいてくれて、Mくんが元気でいるようにって
応援してくれるよ。」
・「○○ちゃんは、お空のお星さまになったの。
お母さんといつも夜に見ていた、あのピカピカのお星さまね。
きっとこれからは、Mちゃん、頑張れ~とお空から見ていてくれるよ。
○○ちゃんは、どのお星さまになったかな?探してみようね。
さあ、お花を飾ってあげましょう!」
おわかれ儀式のアイデア
- メモリアルスペースを作る。
写真、首輪、おもちゃなど飾って、
「これまで楽しかったよ。ありがとう」の気持ちを伝える空間を作りましょう。
お子さんにとって、ペットの死を受け入れる空間であり、少しずつ心に区切りをつくることになりますね。 - お手紙を書く。
幼稚園や保育所では、この方法を一番多くとります。
楽しかった思い出を文や絵にして、感謝の気持ちを伝えるいい方法です。 - 絵本やアルバムを作る。
写真なども入れて、絵本やアルバムを作ると心の整理につながりますね。
作る過程でたくさんの思い出がよみがえり、ペットへの感謝の気持ちが高まっていくでしょう。 - 思い出の場所に行く。
一緒に歩いた散歩道や公園に行って過ごすこともいいですね。
おこさんの気持ちを優先して「○○ちゃんの好きだったところに行ってみようか」
その場所で、同じように遊んだり、お子さんと静かに思い出話をして気持ちに寄り添ってあげましょう。 - 命日(ペットの誕生日や思い出の日でもいいのです)にキャンドルを灯す。
ペットに関わってきた友達、家族で小さな集まりをすると悲しみも少しずつ分け合えます。
「こんなにうちの○○ちゃんは、愛されていたんだ」と心にあたたかさを取り戻すことができますね。

【ペットとのお別れ】気をつけること
- 感情を抑えすぎないように
だいすきなペットがいなくなったのだから、泣いて当然ですね。
ペットとの関わりが長かったり深かったりしたら、寂しくなるのは当然ですよね。
そんな気持ちをしっかり認めてあげることが癒しの第一歩です。
パパやママも同じ気持ちだということを伝えて、一緒に思い出に浸ってあげましょう。
自分の気持ちをわかってくれていると思ったら心が安らぎ、立ち直りも早くなるでしょう。 - ゆっくり日常に戻っていくように
大切なペットが亡くなったということは、喪失感も大きいです。
朝、起きていないことに気づく。幼稚園から帰っていないことに気づく。
そんな場面が一日の中に何度もあり、悲しみがよみがえってくる。
そんな時に、「〇〇ちゃん、ただいま!」とペットに声掛けするとか、
また、飾っている写真の前にお水やお花あげるとかしたら、心の中のペットが喜んでくれていることを実感するようになり、ペットのいない日常を受け入れてくれるようになりますね。
心の中にはいつも一緒にいるよという気持ちで、少しずつ元気なお子さんに戻っていくでしょう。 - なくなったペットの話をすることを恐れない、避けないように
話をすると、また思い出して悲しむのではないかと思って、自然に避けてしまいがちになります。
しかし、語ることでペットの思い出はより深くなります。
自分のことをよくわかってくれるパパやママに寂しさや悲しさを話すだけでも、心は軽くなるものです。
写真を見ながら、「あの時は楽しかったね~」「あんなことして、おもしろかったね」と
自然に思い出し笑いが出てくるようになるといいですね。 - 体調や睡眠の状況に気をつけて
心の悲しみは、体に影響を与えます。
ペットと一緒に寝ていたというお子さんもおられるでしょう。
しばらくは寝る時にそばにいてあげたり、話をしたりして、
寂しさを軽くするようにしてあげてくださいね。 - ペットロスになったらどうしよう
パパやママは、お子さんが幼稚園や学校に行っている間もずっと泣いているのではないかと
心配される方がおられます。
しかし、ペットがいなくなって寂しさはあるけれど、
学校や幼稚園に行って友達と遊んでる間は寂しさを忘れて、
これまで通りに過ごすお子さんがほとんどです。
でも、どうしても家から出たくないとか、通園通学を嫌がるようならば、無理をさせないでいいと思います。
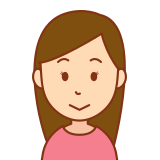
あるお母さんからのお手紙(エピソード)
Y子ちゃんのお母さんから、登園時にお手紙をもらいました。
いつもに比べて、心なしかY子は元気がありません。
お手紙には
「Y子がかわいがっていたペットのチワワがなくなった。
昨日チワワのお葬式をして、Y子はとっても泣きました。
幼稚園に行くと、亡くなったチワワが寂しがるのではと言って少し登園を渋りました。結局、通園バスには乗りましたが、ひょっとしたら園でも泣いてばかりで何もしないかもしれない。
ご迷惑をかけたら申し訳ありません。」というような内容でした。
その日は、Y子ちゃんの様子をできる限り気に留めておきました。
私にもペットをなくした経験があり、Y子ちゃんの気持ちは十分に分かります。
機会をみて、Y子ちゃんに話しかけてみました。
Y子ちゃんとチワワが仲良しだったこと、いなくなったから寂しいこと、
そして先生(保育者)にも同じようなことがあったということなど話すと
Y子ちゃんは、「えっ?先生も泣いたの?」とびっくりした様でした。
「先生も泣いたよ。」
「でも、今はお星さまになって、いつも見ていてくれるから、元気になったよ。」
Y子ちゃんと悲しみの共有でした。
「Y子ちゃんのことも、チワワは見ていてくれるよ。がんばれ!って」
Y子ちゃんに、チワワの絵を描いて見せてもらいました。
「大好きだったんだね。これからもそばにいて見ていてくれるよ」
Y子ちゃんは、それからも元気に登園しました。
Y子ちゃんのお母さんには、「連絡していただいてありがとう」ということと
Y子ちゃんの様子を伝えました。
安心されたようです。
このように、心配な時には、お子さんの様子を幼稚園・保育所や学校に連絡されたなら、いつも以上にお子さんの状況に気をつけておいてもらえますよ。
【ペットとのお別れ】年齢に応じた死に対するとらえ方と対応
ペットとの関わり方、また家庭での生き物に対する考えによって、ペットの死への向き合い方は違ってきます。発達段階に合わせて対応をされることがいいでしょう。
・乳幼児(0~2歳)
死の概念は理解できないが、周囲の不安や悲しみを感覚的にわかる。
大好きなパパやママが泣いているという、いつもと違う雰囲気を敏感に感じ取る。
↓
安心できる環境を整え、スキンシップを大切に!
・幼児(3~5歳)
死を「眠っている」とか「遠くに行った」と混同しがちである。
死は一時的なもので、また戻ってくると考えることもある。
おもちゃが動かなくなったら、電池を入れたらまた動くというような感覚であるため
大した考えもなく生き物を殺してしまうことがある。
そのことを注意すると、電池を入れたらいいと主張する。
↓
「死んだら戻ってこない」という不可逆性をやさしく伝える。

たまごっちが、子どもの世界でブームになった頃から
子どもの死に対する考えが軽くなったように思います。
死んだ生き物を見て、電池を入れたらいいと思う子どもが増えてきました。
死はリセットできないということが理解できない子どもたちが多い。
死が軽く見られるようになった原因の一つとして
ゲームの世界、バーチャルの世界が
子どもの遊びの中に入ったのではないでしょうか?
・児童前期(6~9歳)
死は避けられないものと少しずつ理解し始める。
死を擬人化して「怖い存在」ととらえることもある。
ゆうれいや学校のはなこさんの話を信じて、トイレに行けない子どもがいる。
↓
質問には、正直に丁寧に答える。感情を否定せずに受け止め、少しずつ真実に気付かせていく。
・児童後期(10~12歳)
死を最終的なものと理解して、普遍性(誰にでも訪れる)を認識する。
自分が死んだらということを漠然と考え、解決することはできず悩む子どももいる。
↓
死に対する感情や疑問を話し合える時間をもつ。
絵本や体験を通じて命の大切さを伝える。
・思春期(13歳~)
死の意味や哲学的な問いに関心をもち始める。感情をうちに秘める傾向もある。
↓
対話を通じて価値観を共有し、悲しみを表現する場をつくる。
【ペットとのお別れ】死と向き合うために読みたい絵本
年齢によって、死のとらえ方は違います。
しかし、いろいろな絵本を一緒に読んで、亡くなったペットとの共通点を見つけたりすることもいいですね。
大人が読んでも感動する絵本がたくさんあります。
『わすれられないおくりもの』 スーザン・バーレイ 作
死と向き合うこと、そして残されたものの心の成長を静かに表現しています。
表紙はたくさんの動物たちが、柔らかいタッチで描かれています。
〈あらすじ〉
・主人公の年老いたアナグマは、森の仲間たちから頼りにされいてました。
物知りで優しいアナグマでした。
・アナグマは自分の死が近いことを悟っていました。
しかし、”体はなくなっても心は残る”と信じて、死を恐れていませんでした。
・ある晩、アナグマは「長いトンネルの向こうに行くよ。さようなら」と書いた手紙を残して、
旅立ちました。
・森の仲間たちは深い悲しみに包まれます。
しかし、春が訪れる頃、アナグマとの思い出を語り合うようになりました。
・それぞれが、アナグマから教わったこと(切り紙、スケート、料理など)を思い出し、
彼の知恵や優しさが『贈り物』として心に残っていることに気づきます。
・最後にモグラは、アナグマが亡くなる前に一緒に過ごした丘に登りました。
「ありがとう」と空に向かってアナグマに感謝を伝えたのです。
『100万回生きたねこ』 佐野洋子 作
生と死、そして愛の意味を深く問いかける、哲学的な絵本です。
大人の心にもきっと強く響くでしょう。
『愛すること』『悲しむこと』『命の終わり』を通して、本当の意味での生きるとは何かについて考えさせられます。
〈あらすじ〉
・主人公は、100万回も生きて、100万回も死んだトラ猫です。
・生き返るたびに違う飼い主に愛され、死ぬと泣いてくれるけれど、トラ猫自身は
誰のことも好きではなく、自分だけが大好きでした。
・ある日、トラ猫は誰の飼い猫でもない野良猫として生まれ変わり、初めて『自由』になります。
・周囲のメス猫たちが彼に夢中になる中、唯一彼に興味を示さない白猫に惹かれていきました。
・トラ猫は白猫と心を通わせ、子どもを育て、初めて自分以外の存在を愛することを知りました。
・やがて白猫が亡くなり、トラ猫は初めて涙を流しました。
・そしてトラ猫も白猫のそばで静かに亡くなりました。
もう二度と生き返ることはありませんでした。
他にもありますよ。
絵本を読むことで、ペットとの別れを経験した子どもも、大切な誰かを思う気持ちを育むきっかけになるかもしれませんね。
・『ずっとずっとだいすきだよ』 ハンス・ウィルヘルム 作
・『虹の橋』 葉紹明 作
・『いつでも会える』 菊田まりこ 作
・『いのちの木』 ブリッタ・テッケントラップ 作
・『とびっきりのともだち』 エイミー・ヘスト 作
これらの絵本は、悲しみを無理に消すのではなく、子どもの心に寄り添いながら『命』『愛』『別れ』について考えるきっかけができるでしょう。
読みながら、ペットとの思い出を語り合ったり、「どんな気持ちになった?」と問いかけてみるのも
こころの整理につながるでしょう。
日頃から、このような絵本に触れていることも大切ですね。
まとめ
大好きだったペットが亡くなった時に、どのように対応すればよいか悩むことがあります。
そのペットは、犬や猫といった家で飼われているものだけではありません。
子どもが大切にしている生き物すべてが、ペットなんです。
〈ある男の子は、牛乳パックで作ったパクパク人形を「ペットにしよ!」と通園バックにぶら下げて大切にしていました。〉
虫やザリガニ、メダカなど体が小さいからといって、犬や猫などに比べて命が軽いということもありません。
子どもが大切にしていたペットとして、すべての生き物の命の重みを考えながら死と向き合わせ、命の大切さを伝えたいものです。
この記事では、ペットが亡くなったらどうすればいいか、大人として子どもたちにどのように死を伝えていけばいいかをお伝えしました。
そのためには、子どもたちが死をどのように捉えているかを理解した上で、ペットとのお別れをすることが大切です。
泣くことを我慢させないでもいいです。
大人が子どもの前で涙を流すことを恥ずかしがらないでもいいです。
親子で、大好きだったペットとの思い出に浸りながら、ペットが亡くなった悲しさや寂しさを共有していけば、子どもが一人で悲しみを背負うこともなくなります。
ペットを見送るために、心の温まる儀式をしてあげたいですね。
また、絵本を読むことで、死への向き合い方を学ぶこともできます。
親子で、ペットとのお別れとしっかり向き合うことで
大好きだったペットの存在は、いつまでも大切な思い出となり生きていくことでしょう。
お子さんの心には命の大切さや愛情、感謝の気持ちを育むことになるでしょう。
ペットの死に涙し、心を込めてお別れをしてあげれば、きっと心のあたたかい子どもに育っていくことでしょう。


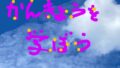
コメント