3歳児が幼稚園入園の時には、おむつが取れていることが条件です。
我が子が、
たまには失敗することはあるけれど、
まだ一人でトイレに行けないとか、
おむつすら完全にはずれていなかったりしたら、パパやママは焦ってしまいますね。
38年の保育経験がある私が、
どうしたらスムーズに楽しくトイレトレーニングができるかという
パパやママの悩みに応えて、絵本をつかって進めていく方法をお伝えします。
絵本で楽しくトイレトレーニング
ウンチやおしっこをテーマにした絵本が、子どもたちは大好きです。
絵本の中に「ウンチ」「おしっこ」「おちんちん」というような言葉が出てくると
すぐに反応し、友達と顔を見合わせて、言い合っては笑い転げています。
これは小学校低学年まで続きますが、どうしてでしょうか?
子どもが「ウンチ」「おしっこ」が好きな理由は、
・大人が過剰に反応してしまうからなんです。
・ウンチやおしっこは、子どもにとって身近な存在です。毎日、出会っていますね。
・ウンチやおしっこは、自分の体から出たものだから愛情を感じているからなんです。
絵本を使ったトイレトレーニングの効果
ウンチやおしっこをテーマにした絵本を、子どもたちはとっても喜んで見てくれます。
だから、トイレに自分で行くという意識付けとして絵本を活用することは、
トイレトレーニングをスムーズに行うために、とってもいい方法です。
絵本をトイレトレーニングに使うわけ
・ウンチやおしっこをテーマにした絵本がたくさん出版されている。
・食べることや排泄の大切さが、子どもに理解しやすいように表現されている。
・ウンチやおしっこについて興味が高まることで、トイレにいくことへの意識付けとなる。
・トイレトレーニングのやり方(おむつからおまるへ、トイレの使い方など)が
子どもの発達に応じてやさしく描かれている。
・親が理屈でトイレトレーニングするよりも、
子どもたちの大好きなキャラクターが伝えた方が、子どもに伝わりやすい。
・いつも身近にある絵本ならば、子どもにとって抵抗なく受け入れられる。
子どもの生活の中でも欠かせない大切な排泄は、基本的生活習慣の一つであり、
それがうまくいかないとパパやママは悩みますよね。
でも大丈夫です!
大人になってまで、一人でトイレに行けないとか、おむつをしている人なんて、
健康な人ならば、ほとんどいません。
でもやっぱり、おむつがはずれて、一人でトイレに行ってくれるようになったら
パパやママはとっても楽になりますよね。
そのためにもトイレトレーニングしたい!
子どもが大好きな絵本を使ってトイレトレーニングしてみませんか?
絵本を一緒に読んでいくことで
子どもがトイレに行ったり、「自分でしたい」という気持ちにさせることが大切です。
ぜひ参考にしてみてください。
トイレトレーニングについては、
保育者、、厚生労働省が出している【保育所保育指針】を参考に考えています。
【保育所保育指針】健康第2章
1歳から3歳未満の保育
⑦排泄の自立に向かう時期には、子どもの「自分でできる」「自分でしたい」という自信や
意欲を育むことが重要になる。
もし、トイレトレーニングがうまくいったら、
きっとお子さんは自信を高め、意欲的に行動することができるようになるでしょう。
トイレトレーニングを始めるには
かつては、何歳になったらおむつを外せるようにしましょう!と指導されることが多かったです。
でも最近は小児科医も、無理にはおむつを外さないでいいと言うようになりました。
トイレトレーニングは、おむつを外すのではなく、おむつは外れるものとした考え方で
一人ひとりの発達に応じてトイレトレーニングをすればいいのです。
いつからトイレトレーニングするか?ではなく
お子さんが、トイレトレーニングできる時期にきたかどうかをしっかり見ていてください。
その時が近づいたならば、まずは、トイレの環境づくりからです。
子どもが楽しめるトイレの環境づくり
① トイレが子どもにとって、楽しい雰囲気であること
トイレが暗かったり、寒かったり、ちょっと臭いがしたりしていませんか?
明るく楽しい雰囲気のあるトイレは
・快適な温度
・あたたかい色の明るさ
・子どもが好きなキャラクターの絵やポスターなどが貼ってある
・大好きな絵本が置いてあるといいです。
② トイレに自分で座ることができるように工夫
トイレに座る時に、抱っこしてもらわなくても自分で上がれますか?
子どもが安定して、便座に座ることができるように工夫しましょう!
・補助便座(大人仕様は、お尻が落ちてしまいそうで怖い!)
・ステッパー・踏み台(高い便座に座るのは、一人では難しい!)
お子さんの体に合ったものを用意しましょう。
③ トイレにゆっくり座っていることができる環境
落ち着いてゆっくり排泄できるトイレ環境ですか?
子どもが小さい時は、排泄は遊びながらでもいいと思います。
・トイレで、絵本タイム(トイレの使い方を知る)
・トイレで、お歌タイム(楽しい気持ちで体の緊張をほぐすリズム)
トイレトレーニングは、焦らず、無理なく、楽しくが基本です。
トイレトレーニングを始める時はいつ?

小児科のお医者さんは、焦らなくてもいいとおっしゃった。
でも、3歳の幼稚園の入園までにはおむつ外したい!
夏までにおむつが外れていなかったら、
幼稚園に行っても、プール遊びをさせてもらえないって・・・
まだ、我が子はおむつでおしっこする方がいいみたい。
おむつ外しは、まだまだかなぁ~

でも、おむつが外れて、自分でトイレに行ってくれるようになったら、
親としたら楽になるよね~
毎月の紙おむつ代も、かなりかかっているからバカにならない。
なんといっても、お出かけする時のおむつという荷物が減る。
暑い夏には、おむつがはずれたら身軽になるのではないかしら・・・
お子さんは、今どのような状況ですか?
心や体、脳の発達の状態には個人差が大きいけれど、
以下のことができるならば、
今です!
トイレトレーニング始めましょう!
① 自分でおしっこに行きたい気持ちになって、「おしっこ」の意思表示ができる。
脳の指令 → おしっこが溜まっているよ → 「おしっこしたい」
② 1~2時間は、おしっこを溜めることができる。
おむつが1~2時間以上濡れていないことで、溜まったかどうか確かめられます。
③ 自分で歩いてトイレに行き、便座に安定して一人で座ることができる。
補助便座や踏み台などを使用する。
④ 人のまねができる。
パパやママがやって見せたら、自分も同じようにしてみようとする。
小さい時から保育所に行っている子どもは、家庭でトイレトレーニングするよりも
早くおむつがはずれている傾向にあります。
それは、同じ保育所の年長児がトイレでおしっこするのを見て、まねをしているからです。
⑤ 服の着脱ができる。
座って着替えてもいい。
パンツが後ろ前になってもいい。
とにかく、自分で脱ぎ着してみようとする。
上記の5つが全部できなくてもいいですが、
脳の「おしっこしたい」という指令を感じられること
おしっこをある程度溜められる体になっていること
この2点については、
トイレトレーニングを始める上では必要条件ですね。
さあ、いよいよトイレトレーニングです。
トイレトレーニング実践してみましょう!
絵本や人形などを使って、トイレに行きたくなるような誘いかけをしてみましょう!
ただし、成功に近づけるためにも、以下の事に気を付けるといいです。

① トイレに誘うタイミングに気を付けましょう。
おしっこに行きたいかどうか気になるところですが、
子どもが遊びに集中している時には、声を掛けないでください。
遊びを邪魔されると、トイレに行くことを嫌がるようになります。
遊びがひと段落した時に、「おしっこに行こうか?」と声を掛けましょう!
② 楽しい声掛けで、トイレに誘ってみましょう。
トイレをしている絵本のページを開いたり、人形などを使って、
さあ、みんなでトイレにGO~!
お散歩気分でいいのです。
そのためにも、トイレは楽しい場所にしておくことが大切です。
保育所や幼稚園のトイレのドアには、かわいい動物の絵が描かれてありますね。
③ 自分で便座に座ってみようという意思を大切にしてあげましょう。
不安定な格好で便座に座るとゆっくり排泄できません。
気持ちも落ち着きません。
また、落ちそうになったりすると、トイレが恐怖の場所に変わります。
慣れるまでは、しっかり補助してあげましょう。
④ おしっこが出たら、しっかり褒めてあげましょう。
自分の意志でおしっこをしたことを認め、
おしっこが出るとはこういう感覚なのかを伝えます。
「おしっこ出たね~」「お利口だったね」
子どももトイレでおしっこするとは、こういうことなのかと分かってきます。
おしっこをトイレでしたらママが喜んでくれた。→ がんばってみよう!
という意欲が芽生えてきます。
⑤ 失敗しても(間に合わなくて漏らした、パンツを濡らした)叱らないでください。
初めは便座に座ることにも時間がかかり、間に合わず、床を汚したりすることもあります。
でも少しずつ上手になることを期待して、次のステップに対して励ましてください。
「ちょっとだけ、おしっこがお外に遊びに行ったね」→ 今度はおしっこ飛ばさないようにするぞ!
トイレの床拭きも、あらかじめ掃除道具を用意しておくと慌てません。
絶対に文句を言わないで、トイレでおしっこをしようとした気持ちを受け止め、褒めてください。
お子さんにその気があれば、トイレの掃除は手伝ってもらうことも可能ですよ。
汚しても、その後きれいにすればいいのだということが分かれば、気が楽になりますね。
絵本「みんなうんち」でトイレトレーニング
「みんなうんち」(五味太郎 作 福音館書店 発行 かがくのとも傑作集) を読んで、
トイレトレーニングです。
子どもたちが大好きな絵本です。
この絵本は、
いろいろないきものが、
どんな形のウンチをしているか、どこでどのようにしているかなど
五味太郎さんのはっきりした色彩の絵で表現され、
子どもたちは1ページ1ページを興味津々で見ています。
〈絵本を見た子どもたちの反応〉
・ いろいろな動物→ ぼく、これ知ってるよ!
・ ふたこぶラクダは、ふたこぶウンチ→ えー? うそー! (笑い)
・ ヘビのおしりはどこ?→
お尻がないよ~!
ウンチせんかったら、体の中がウンチだらけになるよ。
イヤダー!
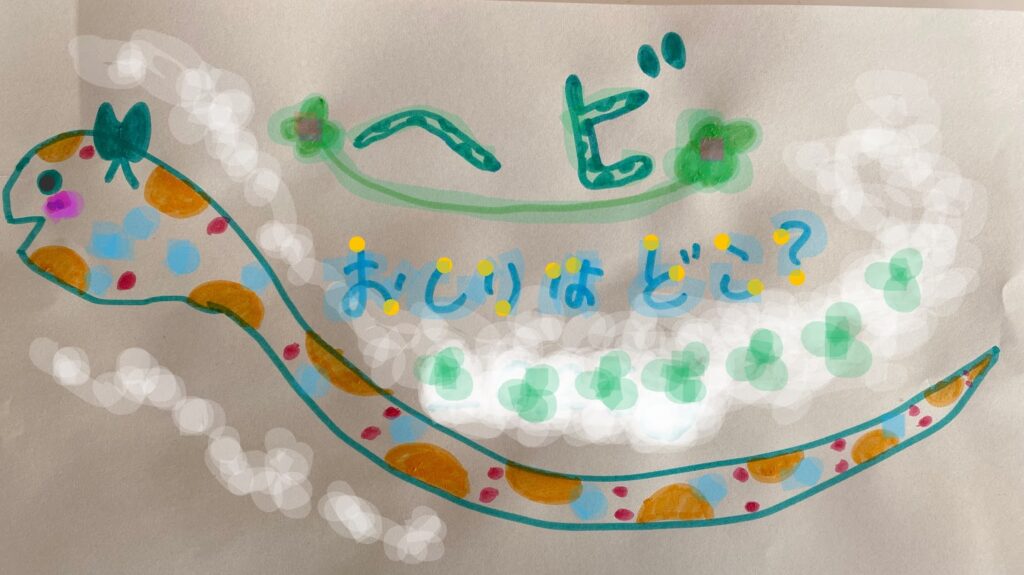
1ページ1ページ子どもたちは、にぎやかに思ったことを話してくれます。
そして、いよいよ、人間もトイレできちんとウンチをするということが描かれている場面では
自分が赤ちゃんだった頃を思い出したり・・・
「ぼく、もうおまる使ってないよ」と誇らしげな表情。
そんな友達を見て、うらやましそうな子ども・・・様々な思いがあります。
絵本を見て
生き物は、生きていく上で、食べる。
そして、排泄をすることはとっても大切だということが分かった子どもたちです。
ウンチをすることは、ちっとも恥ずかしいことではない。
様々な動物がウンチをしている場面に、納得の表情の子どもたちでした。
〈3歳児R子ちゃんの反応〉
R子ちゃんは、食が細く、便秘ぎみ。
ウンチをすることが、時々きつくて、トイレに行きたがりません。
お母さんも悩んでいて、
家にいる時はいいのですが、お出かけの時などは、まだ紙おむつをしていました。
R子ちゃん自身も、自分で進んでトイレに行くことができないことをひけめに感じているのか、
他の活動においても、引っ込み思案の性格になっていました。
そんな時に、幼稚園で「みんなうんち」の絵本を見ました。
お母さんに、その絵本がおもしろかったということ、さらにいろいろな動物が出てきて
ウンチをしてびっくりしたことなどを話しました。
お母さんはさっそく図書館で「みんなうんち」の絵本を借りてきて、家で一緒に読みました。
大人が呼んでもおもしろい内容であり、
お母さんは、R子ちゃんに
「R子ちゃんは、赤ちゃんの時にいっぱいミルクを飲んで、いっぱいウンチやおしっこして
大きくなったんだよ」と話しました。
お母さんは、そのウンチやおしっこがいっぱい出た時には、
R子ちゃんが大きくなってきているから、とっても嬉しかった!とも・・・
決して、たくさん食べてねとか、トイレに自分で行こうねと言ったわけではありません。
でも、R子ちゃんは、ウンチやおしっこがたくさん出たら、
自分が大きくなっていることなんだ
だからお母さんはうれしいんだと、なんとなく理解できたようでした。
これは、絵本の内容ともつながります。
生き物は、生きているから → 食べる → 排泄する
排泄は、とっても大切な事なんだ!という認識ができたようです。
すぐにR子ちゃんの食欲が増して、トイレに自分から進んでいったわけではありませんが
R子ちゃんが、努力し始めたことは確かでした。
少しずつ活動的になれば、食欲も増す。
当然、自然に無理なく排泄できる。
なんといっても、自信をもって行動しようとするR子ちゃんの姿に
トイレトレーニングの効果を感じたお母さんでした。

成功したママ
私には、子ども3人
1人目、2人目の時には、やっぱりうまくいくかどうかと
ちょっと構えていました。
しかし、3人目は「なんとかなるさ~」と気楽にしてみようと思いました。
早めにおまるを出して、意識付けしたのです。
そして、なんとなくオシッコがでそうな時間を見計らって
「おまるって、楽しいよね~」
「ここで、おしっこ、チーってしたら気持ちいいよね~」
この気持ちいいよねという言葉を、そのたびに伝えていきました。
そして、まぐれかもしれませんが
おまるでおしっこが出た時には、「気持ちよかったね~」と褒めました。
おしっこすること ⇒ 気持ちいい事と、我が子の心にインプットされたみたい。
そして、ウンチの時にも
「ウンチ出たら、気持ちいいよね~」
そして、我が子の口からも「気持ちいいする!」
1人目2人目に比べて、本当に気楽で、気が付けば
いつのまにか、トイレトレーニングも終了していましたよ。
排泄することは気持ちいい事なんだということを
気楽に伝えていくことが大切なんですね。
トイレトレーニングに役立つ絵本いろいろ
① 「おまるのぼうけん」 作*さくらももこ 発行所*小学館
② 「うんちマンのひみつのトイレ」 作*ボンドストーン&ホワイト 発行所*あすなろ書房
③ 「トイレタイム*魔法の一歩」 作*小林弘幸 発行所*新星出版社
④ 「おまるのヒーロー*トイレトレーニングの旅」 作*山田真理子 発行所*福音館書店
⑤ 「トイレの冒険*ゆうきとともだちのストーリー」 作*西しまこ 発行所*カクヨム
⑥ 「ぼく、トイレ」 作*飯野由希 発行*ひさかたチャイルド
⑦ 「トイレのおはなし」作 佐藤美代子 発行所 ポプラ社
⑧ 「トイレのおねえさん」作*田中啓文 発行*講談社
もっともっとたくさんありますよ。
いずれも、子どもたちがトイレトレーニングを楽しく学べるように工夫されています。
宇宙のトイレであったり、便秘を治すための体操であったり、
子どもたちの興味を引くように、内容は様々。
最近は、子どもたちの大好きなキャラクター「あんぱんまん」のうんちとの触れ合いを
テーマにしてたくさんの動画も出ています。
それだけ、たくさんのパパやママが、
トイレトレーニングに悩んだり頑張ったりしている証拠ですね。
親子で一緒に楽しく絵本を読みながら、トイレトレーニングやってみましょう!
効果的な絵本の読み聞かせ方法
1 リラックスした雰囲気
お子さんがリラックスして絵本を楽しめるように
・お気に入りの場所(いつも座っている椅子やクッションなど)
・お子さんが大好きなお人形が一緒
・できたら静かな雰囲気
2 一緒に絵本を選ぶ
トイレトレーニングという目的があると、
トイレの使い方を教えたいという意気込みで、本を選んでしまいがちです。
でも、お子さんが好きそうな絵本の中から一緒に選んだ方が、より興味を持って聞いてくれますね。
3 絵本を読む声のトーンや表現を工夫
絵本のキャラクターになりきって、声のトーンや表情を工夫しながら読むといいですね。
文字を間違えないようにと、絵本とにらめっこで読む必要はありません。
いつもお子さんの顔を見て話しているような感じでいいのです。
お子さんに語り掛けるように読んであげると、お子さんは内容に引き込まれていきますよ。
4 繰り返し読む
いろいろな絵本をとっかえひっかえ読む必要はありません。
子どもはお気に入りの本は、何度でも読んでもらいたがります。
繰り返し読むことで、お子さんは内容を覚え、自然にトイレトレーニングのステップを
理解していくようになります。
5 お子さんと対話しながら
絵本の内容によっては、お子さんに質問したり感想を聞いたりするといいでしょう。
そのことで、お子さんがどこまで分かっているか知ることができるし、
お子さんにとっても、トイレトレーニングのステップについて理解が深まっていくと思います。
6 成功体験を褒める
絵本の内容とお子さんの体験が被るような場面があれば、そのシーンを強調して、
キャラクターとの思いを共有しましょう。
お子さんがキャラクター同様に、実際にトイレに成功した時に褒めてあげると、
自信をもってトイレトレーニングに取り組むことになります。
これらの方法を取り入れること
トイレトレーニングがより楽しく効果的になると思いますよ。
また絵本を媒介にして、お子さんのお気に入りのぬいぐるみ人形と対話のような形でもいいです。
ぜひ絵本の読み聞かせて、楽しい時間を過ごし、トイレトレーニングを頑張ってくださいね。
トイレトレーニングは失敗・成功の繰り返し
トイレトレーニングがうまくいったと思っても・・・また、ダメになってしまうこともあります。
4歳児の例です。
いずれも3歳までに、トイレトレーニングはできていました。
① M男くん(4歳児)の場合
おむつを外すタイミングは、ある程度、おしっこの間隔が長くなってからだと
お伝えしました。
M男くんは4歳になっていますが、日ごろはとても明るくて活発な男の子です。
しかし、どうしてもおしっこの失敗が多いのです。
家庭環境も、またM男くんの身体の発達にも大きな遅れはないように思えました。
しかし、頻繁にトイレに行き、なかなか遊びに集中できません。
トイレに行きますが、1回のおしっこの量はちょっとです。
いつもおしっこを漏らさないようにと意識しているために、しょっちゅうトイレに行くのですが
そのことで落ち着きのない性格になってしまうのではと、お母さんは心配して、
お医者さんに診てもらうことにしました。
その結果は、
M男くんの膀胱の発達が十分でないため、おしっこを十分に溜めることができなかったらしいのです。
治療方法としては、
M男くん自身が、下腹部に力を入れて膀胱の筋力を強くするということ。
2時間はおしっこを我慢して、おしっこが膀胱にどのくらい溜まったか計量してみる。
数ケ月という時間はかかりましたが、M男くんの膀胱は少しずつおしっこを溜める力がついて
M男くん自身、遊びに集中できるようになりました。
② A子ちゃん(4歳児)の場合
A子ちゃんも3歳になる前に、紙おむつは外れていました。
問題なくトイレトレーニングは終了したかのように思えたのですが、
ある時からしょっちゅう、おしっこを漏らすようになりました。
トイレには自分で行くこともできていたのに・・・という思いから、
幼稚園でも保育者は気を付けてやり
遊んでいる間も声をかけ、トイレに行くことを促していました。
もちろんA子ちゃんはおしっこに行くことを意識しすぎて、落ち着きがありません。
A子ちゃんの様子に異常を感じたお母さんは、かかりつけの小児科を受診しました。
やはり膀胱機能が弱っているとのことで、薬を処方してもらいました。
しばらくして服薬の効果があり、
おしっこを漏らすことがなくなり、元気に遊ぶことができるようになりました。

③ Y子ちゃん(4歳児)の場合
なんとなくY子ちゃんに近寄ってみると、おしっこの臭いが漂ってきます。
遊びには活発なので、身体機能には異常はないように思われました。
ある冬の事
お母さんからの連絡で、Y子ちゃんが風邪をひいたから欠席しますとのこと。
さらに風邪をひいたのは、Y子ちゃんがおしっこをもらしていたのに、
それを保育者が気付かずに、濡れたパンツのままで過ごしたからだという苦情でした。
4歳になれば、自分の思いを言葉で表現できるようになっています。
もしおしっこに失敗したら、そのことを保育者に伝えて着替えることが普通です。
3歳児のように、トイレに行くように保育者が声を掛けることも少なくなります。
原因は、お母さんの厳しさでした。
Y子ちゃんは、それまでも失敗することはあったのですが、
お母さんに叱られることが怖くて、いつも内緒にしていたのです。
夏の間は、濡れたパンツがいつの間にか乾燥していたこともあるのです。
確かにY子ちゃんのパンツは黄色いシミがついていました。
そんな状況だから、たとえパンツが乾いていてもY子ちゃんからは
なんとなくおしっこの臭いがしていたのです。
濡れたものをいつまでも履いていると風邪をひいたり、
思いっきり遊ぶことができなくなることをY子ちゃんに伝えました。
お母さんにも、たとえ失敗しても叱らないでとお願いしました。
Y子ちゃんは、少し前に妹が生まれて、
赤ちゃんのお世話で忙しそうにしているお母さんの姿を見ています。
お姉ちゃんになったから、お母さんを困らせないようにしたいというY子ちゃん
お姉ちゃんになったから、しっかりして欲しいというお母さんの思いがすれ違っていたのですね。
幼稚園では、パンツが濡れて気持ち悪い時には、きちんと保育者に伝えるように約束させました。
家では、自分で着替えることができるようにバケツに石鹸水などを入れておいておくように
お母さんにお願いしました。
絶対に叱らないで、自分で濡れたバンツを始末をしたことを褒めてあげるようにと。
上記の3例は、3歳児の時にはトイレトレーニングができている子どもたちです。
でも4歳になって、逆戻りしました。
①M男くん ②A子ちゃんは、医療での治療が必要なケース
③Y子ちゃんは、親の養育態度を見直すケース
子どものちょっとした変化を読み取って、ゆっくり楽しくトイレトレーニングをしていきましょう!
まとめ
トイレトレーニングは、何歳になったから始めようというものではありません。
一人一人の子どもの体・脳・心の発達に応じて行われるものです。
その時期が来たから、トイレの使い方を教えるというものでもありません。
子どもがトイレに行きたくなるような環境作りが、とっても大切です。
明るく楽しい雰囲気づくり
安定して排泄できるような補助用具の使用なども
お子さんの体に合うものを用意するといいですね。
この記事では、そのような準備と併行して
お子さんが、より意欲的にトイレトレーニングに取り組めるようにと
絵本を使った実践の一例をお伝えしました。
たくさんの絵本や動画があります。
まずは、お子さんが興味を持ち、楽しく見ることができるものを一緒に探してみましょう!
失敗しても、少しずつ取り組んでいけばいいのです。
トイレトレーニングは、ある日突然、成功するということが多いです。
大人がお手本になって、
仲良しのお友達に刺激を受けて、
その子にあったやり方で進めていくといいですね。
大人になっても、おむつが外れなかった人なんていません。
パパやママは、
お子さんと一緒に、
いろいろな絵本や人形と触れ合いながら、トイレトレーニングを楽しくすすめていきましょう!



コメント